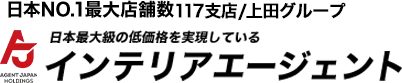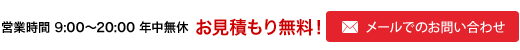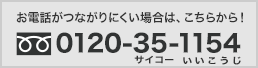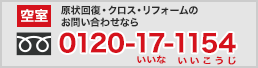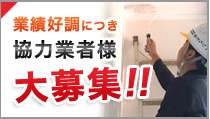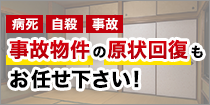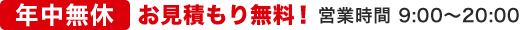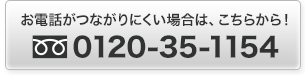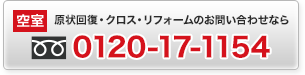原状回復トラブル回避!ルームクリーニング費用相場【完全ガイド】
退去するとき、原状回復やルームクリーニングの費用負担で悩んでいませんか?
実は「通常使用による汚れ」と「特別な破損」では、負担する人が違うのです。
この記事では、国土交通省のガイドラインに基づく原状回復の正しい知識から、クリーニング費用の相場、敷金返還の交渉術まで詳しく解説します。
賃貸物件の退去時に発生する、ルームクリーニングの負担範囲をきちんと理解すれば、不当な請求を防ぎ、余計な出費を抑えられます。
この記事を読めば、あなたも自信を持って退去手続きに臨み、敷金を最大限取り戻せるでしょう。
目次
原状回復とクリーニングの基本
賃貸物件を退去するとき、「原状回復」や「ルームクリーニング」という言葉を耳にし、「どこまで負担する必要があるのだろう?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この章では、賃貸物件の退去時に問題となる「原状回復」と「ルームクリーニング」の基本的な考え方を紹介します。
原状回復とクリーニングの基本には以下の内容があります。
- 原状回復の本当の意味と入居者の義務範囲
- 通常損耗・経年劣化は貸主(オーナー)負担というルール
- ルームクリーニングの必要性と費用負担の考え方
原状回復義務の定義を解説
「原状回復」という言葉から、多くの人は「入居時と同じ新品の状態に戻す」ことだと誤解していますが、それは正しくありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、原状回復とは「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使用による損耗を復旧すること」と定義されています。
つまり、日常生活で自然に発生する経年劣化や通常の使用による損耗は、原状回復の対象ではないのです。
この考え方は民法621条にも明記され、法的にも裏付けられています。
例えば、長年住んでいて壁紙が日焼けで変色したり、普通に置いていた家具の重みで床が少しへこんだり、エアコンが古くなって効きが悪くなったりするのは、基本的に大家さん(貸主)の負担です。
これらは「通常損耗」や「経年劣化」と呼ばれるものです。
しかし、うっかり壁に物をぶつけて穴を開けてしまったり、飲み物をこぼしたシミを放置してしまったり、契約で禁止されているにも関わらずペットを飼って柱を傷つけてしまったりした場合は、入居者(借主)の責任で修繕することになります。
これは「故意・過失による損耗」や「善管注意義務違反」にあたります。
たとえ賃貸借契約書に「原状回復一切を借主負担」と記載があっても、それだけで全ての費用を負担する必要はありません。
自分の責任範囲を正しく理解し、不当な請求から身を守りましょう。
通常損耗・経年劣化との違い
原状回復の負担を考える上で重要なのが、「通常損耗・経年劣化」と「故意・過失による損耗」の区別です。
通常損耗とは、時間の経過や日常的な使用で自然に生じる劣化のことで、原則として大家さん負担となります。
これは長期間の居住により避けられない損耗であり、その修繕費用はあらかじめ賃料に含まれていると考えられているからです。
さらに知っておきたいのが、「耐用年数」と「減価償却」という考え方です。
これは、壁紙や設備などにはそれぞれ「価値が持続する期間(耐用年数)」が決められていて、時間が経つにつれてその価値が下がっていくというものです。
そして、耐用年数を過ぎたものの価値は、基本的に1円(ほぼゼロ)として扱われます。
もし6年以上住んでいれば、その壁紙の価値はほぼ1円になっているため、たとえ過失で汚してしまったとしても、原則として交換費用を全額負担する必要はないのです(負担は1円)。
フローリングやエアコンなどの設備も同様に、入居期間や経過年数によって負担割合が大きく変わります。
退去時に修繕費用の請求を受けた場合は、その損耗が本当に自分の過失によるものか、また物件の経過年数が考慮されているかをしっかりチェックしましょう。
以下に貸主負担と借主負担の具体例を表で示します。
|
損耗・汚損の具体例 |
主な原因 |
原則的な費用負担者 |
|
壁紙の日焼け・色あせ |
経年劣化 |
貸主 |
|
家具の設置による床・カーペットのへこみ、 設置跡 |
通常損耗 |
貸主 |
|
エアコンの内部洗浄(通常の使用に伴うもの) |
通常損耗 |
貸主 |
|
畳の表替え、裏返し(通常の使用による摩耗・変色) |
経年劣化・通常損耗 |
貸主 |
|
テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の電気ヤケ |
通常損耗 |
貸主 |
|
借主がうっかり飲み物をこぼしたことによるシミ(放置せずすぐ拭き取ったが残った) |
過失の程度による |
貸主/借主 |
|
壁に物をぶつけてできた穴・傷 |
故意・過失 |
借主 |
|
タバコのヤニによる壁紙の黄ばみ・臭い |
善管注意義務違反・用法違反 |
借主 |
|
ペットによる柱・壁の傷、臭い(ペット飼育可物件でも通常使用を超える場合) |
善管注意義務違反・用法違反 |
借主 |
|
結露を放置したことによるカビ・シミの拡大 |
善管注意義務違反 |
借主 |
|
換気扇の油汚れ(日常の清掃を怠った結果、固着したもの) |
善管注意義務違反 |
借主 |
|
鍵の紛失・破損による交換 |
過失 |
借主 |
ルームクリーニングの必要性
賃貸物件の退去時に話題になるのが「ルームクリーニング(ハウスクリーニング)」の費用負担です。
ルームクリーニングとは、次の入居者のために専門業者が行う徹底的な清掃のことですが、その費用負担は誰がすべきなのでしょうか。
まず大切な原則として覚えておきたいのは、「普段の生活で汚れた程度を超えるような、特別な清掃が必要な場合」を除いて、専門業者によるルームクリーニング費用は貸主(大家さん)の負担が基本だということです。
「じゃあ、契約書に特約があったら絶対払わないといけないの?」と不安になるかもしれませんが、そうとも限りません。
その特約が法的に有効と認められるためには、いくつかの条件があります。
例えば、契約書にクリーニング費用を負担することがはっきり書かれているだけでなく、その金額や清掃範囲が具体的であること、契約を結ぶ際にその特約について十分な説明があり、あなた自身が納得して同意したことなどが重要になります。
「クリーニング費用は借主負担」とだけ書かれ、金額の記載がない特約は、消費者契約法に照らして無効となる可能性があります。
契約書を確認し、特約が曖昧な場合は交渉の余地があるでしょう。
また、換気扇の油汚れや水回りのカビなど、自分でできる範囲の清掃を退去前に徹底することで、追加費用を抑えられます。
ルームクリーニング費用負担の原則
「退去時のルームクリーニング費用、結局誰が払うのが一般的なの?」これは多くの方が抱く疑問でしょう。
この章では、賃貸物件の退去時におけるルームクリーニング費用の負担原則について紹介します。
ルームクリーニング費用負担の原則の内容は以下の3つです。
- 国土交通省のガイドラインが示す費用負担の基本的な考え方
- 東京都など地方自治体独自のルールと規制
- 原則として貸主負担となる法的・経済的根拠
国交省ガイドライン上の原則
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、専門業者によるルームクリーニング費用は、原則として貸主(大家さん・オーナー)が負担すべきものとされています。
このガイドラインでは、通常の使用による汚れの回復費用は「賃料に含まれている」という考え方が示されています。
つまり、入居者が日常的な清掃を行っていれば、退去時の専門業者によるハウスクリーニングは、次の入居者を迎えるための貸主側の準備行為であり、その費用は賃料収入から支払うべきとの考え方です。
2020年の民法改正でもこの原則が明確化され、法的根拠が強まりました。
入居者が行うべき「通常の清掃」とは、日常的に行う掃除と、退去時に私物を全て撤去し、簡単な掃除を行う程度とされています。
換気扇内部の油汚れ除去、浴室のカビ取り、エアコン内部洗浄などの専門的清掃は、入居者が特別な汚損(油汚れの放置、換気不足によるカビの拡大など)を起こさない限り、貸主負担が原則です。
ただし、この原則に対して、賃貸借契約書の「特約」によって例外が設けられることが多いのが実情です。
国交省ガイドラインは法的拘束力をもつ法律ではなく指針であるため、特約に合意した場合はその効力が問題となります。
東京都ガイドラインでの扱い
東京都では「賃貸住宅紛争防止条例」(通称:東京ルール)を定め、原状回復に関する説明義務を不動産業者に課しており、ルームクリーニング費用についても、より透明性の高い説明を求めています。
この条例は国交省ガイドラインの考え方を基本としつつ、特に「特約」の内容について契約時の説明を法的に義務付けている点が特徴です。
特に人口の多い東京のような大都市では、残念ながら賃貸に関するトラブルも少なくありません。
そこで、この「東京ルール」は、契約を結ぶ前に入居者に対して費用負担のルールをはっきりと説明することを不動産業者に義務付けることで、後々の「言った・言わない」といったトラブルを防ごうという狙いがあるのです。
宅地建物取引業者は、退去時のルームクリーニング費用を含む原状回復の基本的考え方や特約の内容を書面で説明する義務があるのです。
具体的には、契約時に「原状回復費用説明書」などの書面を交付し、ルームクリーニング費用の金額や範囲、作業内容などを明確に説明することが求められます。
例えば「退去時にハウスクリーニング費用として55,000円を負担する」といった具体的な金額設定や「キッチン・浴室・トイレの清掃一式」といった範囲の明示が必要です。
東京都以外にも、神奈川県、千葉県、埼玉県など近隣の都県でも、同様の説明書式を使用する不動産会社が増えています。
貸主負担が基本となる理由
ルームクリーニング費用が原則として貸主負担となるのには、いくつかの重要な理由があります。
ルームクリーニング費用が原則として貸主負担となる主な理由は以下の3点です。
- 賃貸経営上の経費: 物件の維持管理費用として、定期的な清掃やメンテナンスのコストは賃料収入から賄われるべき経費と見なされるため。
- 貸主の義務: 次の入居者を迎えるための準備行為(清掃を含む)は、賃貸物件を賃貸可能な状態に保つという貸主の責任の一環であるため。
- 公平性の観点と法的解釈: 入居者が標準的な清掃を行っていれば、専門業者によるクリーニングは通常損耗の範囲内であり、民法上も貸主負担が公平とされ、実際の裁判例や消費者契約法の観点からもこの考え方が支持されているため。
これらの理由から、ルームクリーニング費用は原則として貸主が負担すべきものと考えられています。
まず、賃貸経営において物件の維持管理は不可欠であり、そのための清掃費用は家賃収入で賄うべき経費とされます。次に、物件を常に貸し出せる状態に保つことは貸主の責任であり、次の入居者のための清掃もその準備行為に含まれます。
最後に、入居者が通常の清掃を行っていれば、専門業者によるクリーニングは通常損耗と見なされ、民法や過去の判例、消費者契約法の観点からも貸主負担が妥当と判断されているのです。実際の裁判例でも、「借主が負担すべきなのは入居時の状態からの悪化分のみ」という判断がなされることが多く、通常の使用による汚れは悪化ではなく経年変化と見なされます。
2005年以降の判例では、クリーニング特約について、有効となる条件を厳格に判断する傾向があり、説明不足や金額不明確など特約の不備を理由に無効とされるケースが増えています。
消費者契約法の観点からも、一方的な負担を借主に求める特約は見直されているのです。
借主負担になる特約の有効条件
契約書に「ハウスクリーニング費用は借主負担」と書かれていても、その特約が必ずしも法的に有効とは限りません。
この章では、賃貸物件の退去時における原状回復費用やルームクリーニング費用を借主負担とする特約の有効条件について紹介します。
借主負担になる特約の有効条件のポイントは以下の4つです。
- 特約が法的に有効と認められるための4つの要件
- 契約書における具体的な金額や範囲の明記方法
- 借主の善管注意義務違反が認められるケースと法的な影響
- 裁判所で特約が無効とされた実際の判例と教訓
有効な特約と認められる要件
賃貸借契約におけるルームクリーニング費用を借主負担とする特約が有効となるためには、厳格な条件を満たす必要があります。
国土交通省のガイドラインや裁判例によれば、有効と認められるための要件は主に4つあります。
ご自身の契約書と照らし合わせてみてください。
- 特約を結ぶ必要性があり、内容が一方的すぎないこと(必要性・合理性)
- あなたが義務の内容をちゃんと理解していたこと(借主の認識)
- あなたが負担することに納得して同意したこと(借主の意思表示)
- 負担する内容・範囲・金額が具体的に書かれていること(具体性)
これらのポイントについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
まず「必要性と合理性」とは、特約で費用負担を求める客観的な理由があり、その内容があなたにとって一方的に不利なものでないことが大前提です。
次に「借主の認識」については、「通常の原状回復とは違う、特別な費用を負担するんだ」ということを、契約を結ぶときにあなたがはっきりと理解する必要があります。口頭での説明だけでなく、書面での説明も重要視されます。
「借主の明確な意思表示」では、ただ契約書にサインしただけでなく、「この特約の内容を理解し、費用を負担することに同意します」というあなたの明確な意思があったことが求められます。
最後に「負担内容の具体性」は、契約書に「クリーニング費用は〇〇円」といった具体的な金額や、「〇〇と△△の清掃費用」のように範囲がはっきりと書かれている必要があります。
「実費負担」のような曖昧な記載は無効とされる可能性が高いです。
これらの要件は消費者契約法第10条の趣旨にも沿うものであり、曖昧で高額なクリーニング特約は無効とされる可能性が高いです。
賃貸契約締結時には、特約の内容を確認し、説明を求めることが重要です。
契約書での明確な記載方法
クリーニング特約が有効となるためには、契約書での記載方法が極めて重要です。
では、具体的に契約書にはどのように書かれていれば良いのでしょうか?
ポイントは以下の4つです。
- 具体的な金額が書かれていること: 「退去時のハウスクリーニング費用として、〇〇円(消費税込)を負担する」のように、明確な金額が数字で記載されている
- 清掃の範囲が示されていること:「上記費用には、キッチン、浴室、トイレ、洗面所の清掃を含む」など、どの範囲の清掃に対する費用なのかが具体的にわかるように書かれている
- 負担を求める理由が合理的であること: 「本来は貸主が負担すべき費用だが、借主の意向も踏まえ、次の入居者のために特約として負担を求める」といった、負担を求めること自体に一定の合理性が認められる説明が必要
- 金額が相場からかけ離れていないこと:提示されている金額が、一般的なハウスクリーニングの相場と比べて、あまりにも高額すぎない
有効な記載例としては、「退去時に専門業者によるルームクリーニング費用として、1Kの場合30,000円を借主が負担する。
この費用にはキッチン、浴室、トイレの清掃を含む」といった具体的なものが挙げられます。
反対に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」といった曖昧な記載は、裁判所によって無効と判断される可能性が高いでしょう。
善管注意義務違反時の扱い
借主には「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」があり、この義務に違反して汚損を発生・拡大させた場合は、ルームクリーニングに関する特約の有無にかかわらず、その修復費用を負担する必要があります。
善管注意義務とは、賃貸物件を社会通念上要求される程度の注意をもって管理・使用する義務のことで、民法上の基本原則です。
この義務違反として典型的なのは、キッチンの換気扇を掃除せず油汚れを蓄積させたり、浴室の換気を怠りカビを放置したりするケースです。
また、水漏れに気づきながら放置して床材を腐食させたり、ペット禁止物件でペットを飼育して傷や臭いをつけたりした場合も、善管注意義務違反となります。
特に禁煙物件での喫煙による壁紙のヤニ汚れは、明らかな契約違反として全額借主負担になる可能性が高くなります。
こうした場合、通常のクリーニングでは対応できない特別な清掃や修繕が必要となるため、その費用は借主負担です。
入居中は定期的な清掃や換気を行い、不具合があれば速やかに報告することが重要です。
特約が無効とされた判例紹介
過去の裁判例では、クリーニング特約や原状回復に関する特約が無効とされるケースが少なくありません。
特に2000年代以降、消費者契約法の施行も影響し、借主保護の観点から特約の有効性を厳格に判断する傾向が強まっています。
代表的な判例として、最高裁平成17年12月16日判決があります。
この事例では「賃借人は通常損耗についても原状回復義務を負う」という特約について、通常損耗の範囲や金額等が契約書に具体的に明記されておらず、借主が明確に認識していたとはいえないとして無効と判断されました。
また、東京地裁平成21年9月25日判決では、「明け渡し時にハウスクリーニング費用を支払う」という特約について、金額の明示がなく説明も不十分だったとして無効とされています。
裁判所は特約の有効性を判断する際、契約時の説明状況、特約の具体性・明確性、金額の相当性、借主の理解と合意の有無などを総合的に考慮します。
契約時には特約の内容を詳細に確認し、退去時に不当な請求を受けた場合は、こうした判例を参考に交渉することも可能です。
ルームクリーニング費用の目安
ルームクリーニングの具体的な金額が気になる方も多いでしょう。
この章では、賃貸物件の退去時におけるルームクリーニング費用の相場や内訳について紹介します。
ルームクリーニング費用については以下の内容があります。
- 間取りやエリアごとの平均的な費用相場
- 一般的なハウスクリーニングに含まれる作業内容と範囲
- 追加料金が発生するケースと特殊清掃の費用
間取りごとの費用相場一覧
賃貸物件を退去する際のルームクリーニング費用は、間取りによって大きく変わります。
一般的な相場は、1Rや1Kのワンルームタイプで15,000~35,000円、1DK・1LDKで20,000~50,000円、2DK・2LDK・3Kで30,000~70,000円、3LDK以上の広い物件では50,000円を超えることが多いです。
ただし、これはあくまで目安です。 一つ注意しておきたいのは、管理会社から「うちが指定する業者で」と言われた場合、一般的な市場の相場よりも2~3割ほど高くなることがある点です。費用差が生じる要因としては、部屋の広さだけでなく、物件の種類、物件の状態、汚れの度合い、地域差、業者の規模、依頼時期なども影響します。
特に引っ越しシーズンである3~4月や9~10月は需要が集中するため料金が上昇する傾向があります。
費用を抑えるためには、契約時に特約の有無と金額を確認し、可能であれば複数の業者から相見積もりを取ることが効果的です。
自分で業者を選べる場合は管理会社指定より安くなることが多いですが、清掃品質に問題があると判断された場合、再清掃を求められるリスクもあるため、評判の良い業者を選ぶことが重要です。
以下に間取り別ルームクリーニング費用相場を表で示します。
|
間取り |
費用相場(円) |
|
1R・1K |
15,000円 ~ 35,000円 |
|
1DK・1LDK |
20,000円 ~ 50,000円 |
|
2DK・2LDK・3K |
30,000円 ~ 70,000円 |
|
3LDK以上 |
50,000円 ~ |
|
一戸建て |
集合住宅より高め |
※上記の金額はあくまで目安であり、物件の状態や地域、業者によって変動します。
一般的なクリーニングの作業内容
退去時のハウスクリーニングは、一般的に「ベーシッククリーニング」と「オプション清掃」に分かれています。
基本パッケージには、部屋全体の床・壁・天井の清掃、キッチン・浴室・トイレなどの水回り清掃、窓・網戸・サッシの清掃、玄関・下駄箱の清掃などが含まれるのが標準的です。
具体的には、床のクリーニング(フローリングの水拭きや畳の清掃)、壁のホコリや手垢の除去、キッチンのシンクやコンロ周りの清掃、浴室の浴槽・壁面・床・鏡の清掃、トイレの便器・タンク・床の清掃、洗面台と鏡の清掃、窓ガラスやサッシの清掃などが基本作業として行われます。
しかし、業者によって「基本パッケージ」に含まれる範囲は若干異なるため、見積もりを取る際には具体的な作業内容を確認することが重要です。
また、エアコン内部洗浄、換気扇(特にキッチンのレンジフード)の分解洗浄、照明器具の分解清掃などは、多くの場合オプション扱いとなり、別途費用が発生します。
これらのオプション清掃は、基本料金に含まれると思い込んでいたケースもトラブルの原因となりやすいため、事前に「何が含まれて何が含まれないか」を明確にしておくことが大切です。
以下に一般的なクリーニング作業範囲を表で示します。
|
清掃場所 |
主な作業内容例 |
オプションになりやすい項目例 |
|
キッチン |
シンク磨き、 ガスコンロ・IHコンロ清掃、 収納扉表面拭き、床拭き、照明拭き |
換気扇(レンジフード)分解洗浄、排水溝内部、オーブン等家電内部 |
|
浴室 |
浴槽洗浄、 壁・床・天井のカビ取り(軽度)、 鏡磨き、排水口清掃、換気扇表面清掃 |
エプロン内部高圧洗浄、 浴室乾燥機分解洗浄 |
|
トイレ |
便器内外清掃、タンク表面拭き、 床拭き、換気扇表面清掃 |
温水洗浄便座ノズル分解洗浄、タンク内部 |
|
洗面所 |
洗面ボウル磨き、鏡磨き、 収納扉表面拭き、床拭き |
洗濯パンの徹底清掃 |
|
床 |
フローリング水拭き・乾拭き、 畳拭き掃除(掃除機掛け)、 カーペット掃除機掛け |
ワックスがけ、カーペットのシミ抜き(特殊なもの) |
|
壁・天井 |
ホコリ除去、簡易的な拭き掃除 |
ヤニ汚れの特殊清掃、 クロスの部分補修 |
|
窓・サッシ |
窓ガラス内側拭き、サッシレール清掃、 網戸清掃 |
窓ガラス外側拭き(高所は別途)、 雨戸・シャッター清掃 |
|
玄関 |
玄関たたき清掃、下駄箱内外拭き |
|
|
その他 |
照明器具表面拭き、 ドア・建具拭き、 ベランダ掃き掃除(簡易) |
エアコン内部洗浄 |
※業者やプランによって基本作業の範囲は異なります。
必ず見積もり時に確認してください。
追加費用が発生するケース
通常のルームクリーニング費用に加えて追加料金が発生するケースには主に以下のようなものがあります。
まず、特殊な汚れや損傷の除去が必要な場合です。
特に喫煙による壁紙のヤニ汚れ(壁紙1帖あたり3,000~5,000円、または通常料金の30~50%増)、ペットの臭いや汚れ(通常料金の30~50%増)、カビの特殊清掃(5,000~15,000円程度)などが代表例です。
その他、普段あまり掃除しないような特別な場所の清掃も、オプションとして追加料金がかかることが一般的です。
例えば、エアコンの内部洗浄(1台あたり8,000円~15,000円程度)、キッチンの換気扇(レンジフード)の分解洗浄(5,000円~15,000円程度)などがこれにあたります。
ただし、エアコン内部洗浄は原則として貸主負担とされています。詳しくは前の章をご確認ください。
さらに、入居中のクリーニングは家具の移動や養生が必要なため割増料金(通常の20~30%増)となり、緊急対応や休日作業も追加費用の対象です。
これらの追加費用を抑えるためには、日常的な清掃習慣が重要で、特にキッチンの油汚れや水回りのカビは定期的なケアで蓄積を防げます。
退去が決まったら早めに自分でできる範囲の清掃を行い、特に水回りの頑固な汚れに注力するとよいでしょう。
見積もりを取る際には追加費用が発生しそうな箇所を事前に伝え、総額を把握しておくことが大切です。
以下に追加費用が発生する主なケースと費用目安を表で示します。
|
追加費用が発生するケース例 |
追加費用の目安例 |
|
喫煙による壁紙全体のヤニ汚れ・臭い |
通常料金の30~50%増、または1帖あたり数千円 |
|
ペットによる広範囲の傷・汚れ・強い臭い |
通常料金の30~50%増、または別途見積もり |
|
長期間放置された頑固なカビ(浴室、壁など) |
5,000円 ~ 15,000円程度、または別途見積もり |
|
通常清掃で落ちないキッチンの油汚れ(レンジフード内部など) |
換気扇分解洗浄として 5,000円 ~ 15,000円 |
|
エアコン内部の分解洗浄 |
1台あたり 8,000円 ~ 15,000円 |
|
特殊な素材の床・壁のクリーニング |
別途見積もり |
|
荷物が残っている状態での作業(入居中クリーニング) |
通常料金の20~30%増 |
|
深夜・早朝・休日の指定作業 |
割増料金(業者による) |
|
緊急依頼(即日・翌日など) |
割増料金(業者による) |
|
ゴミ屋敷状態の清掃・ゴミ処分 |
大幅な追加料金、または対応不可の場合あり |
※上記の金額はあくまで目安であり、汚れの度合いや業者によって大きく変動します。
原状回復トラブルを回避する方法
「退去時にお金で揉めたくない…」誰もがそう思いますよね。
この章では、賃貸物件の退去時に発生しやすい原状回復トラブルを未然に防ぐための具体的な方法について紹介します。
原状回復トラブルを回避する方法には以下の内容があります。
- 入居前後の物件状態を証拠として残すための写真撮影の重要性とポイント
- 退去時の立ち会い検査での対応方法と注意すべき事項
- 契約締結時に確認すべき原状回復やクリーニング特約のチェックポイント
- トラブルが発生した際に相談できる公的機関や専門家のリスト
入居時の写真撮影は必須
賃貸物件に入居したら、まず部屋全体の状態を写真や動画で記録しておくことが重要です。
これは退去時の原状回復トラブルを防ぐための最も効果的な対策です。
退去時のトラブルの多くは「この傷はいつからあったのか」という認識の違いから発生するからです。
契約時のチェックリストだけでは細かい部分までカバーできないことが多く、写真がなければ立証責任は借主側にあり、不利な立場に立たされます。
撮影すべき箇所は、壁・床・天井の傷や汚れ、キッチン・浴室・トイレなどの水回り、窓やドアなどの建具、エアコンや給湯器などの設備機器の状態です。
撮影する際のポイントとして、日付がわかるように撮影すること、スマートフォンのタイムスタンプ機能を使うか、日付入りの新聞やメモを一緒に写すこと、壁や床の傷は全体の位置関係がわかる写真と細部がわかる接写の両方を撮ることが有効です。
撮影した写真・動画はクラウドストレージなどにバックアップし、契約期間中は保管しましょう。
また、入居直後に発見した不具合は速やかに管理会社やオーナーに報告し、その記録も保存しておくことで、より確実な証拠となります。
退去時の立ち会いを必ず実施
退去時の立ち会い検査は、原状回復に関するトラブルを未然に防ぐために重要です。
できる限り借主本人が立ち会い、管理会社やオーナーと一緒に物件の状態を確認することで、修繕が必要な箇所とその費用負担について明確にできます。
立ち会いがない場合、後日「キズがあった」「汚れがひどかった」などと一方的に判断され、過大な費用を請求されるリスクが高まります。
立ち会い検査の準備としては、退去の1~2週間前に管理会社に連絡して日程を調整し、当日は賃貸借契約書、入居時のチェックリスト、写真・動画、返却する鍵を持参しましょう。
立ち会い時には、各部屋を順に回りながら壁や床の傷、設備の状態を確認し、可能であればスマートフォンで録音・録画するとよいでしょう。
ただし事前に相手の了承を得てください。
修繕箇所と費用の概算を確認することは重要ですが、その場で安易に費用負担に同意せず、「詳細な見積もりを送ってください」と伝えるのがベストです。
書類への署名を求められた場合、「確認した」という事実だけを証明する書類なら署名してもよいですが、費用負担に関する合意を含む書類への署名は慎重にすべきです。
契約書特約の確認ポイント
賃貸物件の契約時には、原状回復やルームクリーニングに関する「特約」の内容を詳細に確認することが重要です。
国土交通省のガイドラインでは、通常損耗や経年劣化の修繕費用は原則として貸主負担とされていますが、「特約」によってこの原則が覆されることがあります。
しかし、すべての特約が有効なわけではなく、裁判例では「金額が不明確」「説明不足」などの理由で無効とされるケースも多いのです。
契約書で確認すべき特約のポイントとして、まず「ハウスクリーニング費用」に関する特約では、具体的な金額が明記されているか、清掃範囲が明確か、入居年数による減額規定があるかを確認します。
次に「通常損耗の修繕費用」に関する特約では、対象箇所が明記されているか、金額や算定方法が具体的か、経過年数(減価償却)が考慮されているかをチェックします。
「敷金返還条件」に関する特約では、敷金から控除される項目と返還時期・方法が明記されているかを確認しましょう。
特約が怪しいと感じる「レッドフラッグ」として、金額の記載がない、市場相場より著しく高額、入居年数にかかわらず定額、契約時に具体的な説明がなかったなどの場合は注意が必要です。
困った時の相談窓口リスト
原状回復やルームクリーニング費用について管理会社やオーナーとトラブルになった場合、適切な相談窓口に早めに相談することが問題解決の近道です。
まず無料で相談できる公的機関として、国民生活センターや地域の消費生活センター(消費者ホットライン「188」)があります。
消費者保護の観点からアドバイスを受けられますが、基本的には助言にとどまります。
地方自治体の住宅課や建築課など相談窓口も無料で利用でき、地域の住宅事情に詳しいスタッフが対応してくれます。
また、仲介した不動産会社が宅建協会の会員なら、宅地建物取引業協会(宅建協会)に相談することも可能です。
法的な解決を検討する場合は、法テラス(日本司法支援センター)に連絡すると、適切な法律相談窓口を紹介してもらえ、低所得者向けの無料相談や費用立替制度もあります。
より専門的な対応が必要なら弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。
費用はかかりますが(初回相談30分で5,000円程度)、交渉や訴訟代理など実務的なサポートが得られます。
60万円以下の請求なら少額訴訟も選択肢となり、比較的簡易な手続きで解決できる可能性があります。
どの窓口に相談する場合も、契約書や写真などの証拠資料を準備しておくとスムーズです。
主な相談窓口一覧
|
相談窓口名 |
主な相談内容 |
連絡先・アクセス方法例 |
費用 |
|
国民生活センター・地域の消費生活センター |
賃貸契約に関するトラブル全般、 不当な請求、 クーリングオフなど消費者問題全般 |
消費者ホットライン「188」(局番なし) 各自治体のウェブサイトで検索 |
原則無料 |
|
法テラス (日本司法支援センター) |
法律相談(弁護士・司法書士紹介)、 経済的に余裕がない場合の無料法律相談・費用立替 |
電話:0570-078374(おなやみなし) |
条件によ り無料 |
|
宅地建物取引業協会(宅建協会・全日本不動産協会など) |
仲介した不動産業者とのトラブル(協会会員の場合)、 苦情相談 |
各都道府県の宅建協会ウェブサイトで検索 例:東京都宅地建物取引業協会など |
原則無料 |
|
各自治体の住宅相談窓口 |
賃貸住宅に関する一般的な相談、 地域の条例に基づくアドバイス |
各市区町村の役所ウェブサイト (「住宅課」「建築指導課」などで検索) |
原則無料 |
|
弁護士・司法書士 |
専門的な法律相談、交渉代理、 訴訟代理など |
各地域の弁護士会・司法書士会ウェブサイトで検索、 または法テラス経由で紹介 |
有料 (相談料の目安あり) |
※相談内容や利用条件によって対応が異なる場合があります。事前に各窓口にご確認ください。
クリーニング費用を抑えるコツ
退去時の出費は、できるだけ抑えたいものです。
この章では、賃貸物件の退去時におけるルームクリーニング費用を効果的に抑えるための具体的な方法について紹介します。
クリーニング費用を抑えるコツには以下の内容があります。
- 自分で効果的に清掃できる箇所と専門業者に任せるべき部分の見極め方
- 複数の業者から見積もりを取得して費用を比較する方法とそのメリット
- 依頼時期や条件によって変動する料金体系と予約のタイミング
- 敷金精算時に不当な請求を防ぎ、適正な費用負担を実現するための交渉術
自分で清掃すべき箇所は?
退去前の自分でできる清掃を徹底することで、プロによる追加クリーニング費用を大幅に削減できます。
特に効果的なのは、キッチンの油汚れ対策です。
換気扇フィルターはお酢に一晩漬け置きすると油汚れが落ちやすくなり、ガスコンロ周りは重曹ペーストを使うと効果的です。
また、浴室やトイレのカビ取りも自分でできる重要な作業です。
市販のカビ取り剤を使って壁面や天井のカビを除去し、排水口のヌメリや髪の毛もしっかり取り除きましょう。
洗面台や鏡の水垢はクエン酸水で落とせることが多いです。
床や壁の清掃も基本的には自分でできます。
フローリングは固く絞った雑巾で水拭きし、壁の手垢はメラミンスポンジで軽く擦るだけで目立たなくなります。
畳は目に沿って掃除機をかけ、同じく固く絞った雑巾で拭くことが効果的です。
ただし、エアコン内部洗浄や換気扇(特にレンジフード)の分解洗浄、高所の照明器具など専門知識や工具が必要な作業は無理に挑戦せず、専門業者に任せたほうが安全です。
日常的な汚れを放置すると「善管注意義務違反」とみなされ、入居者負担になる可能性があるため、退去の2~3週間前から計画的に清掃を始めることをおすすめします。
複数業者から見積もりを取る
退去時のルームクリーニング費用を節約するなら、複数の業者から見積もりを取ることが非常に効果的です。
管理会社が指定する業者は、一般的な市場価格より20~30%ほど高額になる傾向があります。
これは管理会社との関係性や手数料の上乗せなどが理由として考えられます。
賃貸契約書に「指定業者必須」という明確な記載がない場合は、積極的に相見積もりを取得すべきでしょう。
最低でも3社以上から見積もりを取るのが理想的です。
例えば、1Kの築10年物件の場合、管理会社指定業者では35,000円前後が相場ですが、大手クリーニング会社なら28,000円程度、地域密着型の業者では22,000円程度で依頼できるケースも少なくありません。
見積もりを取る際には、基本料金に含まれる清掃範囲(エアコンや換気扇は含まれるのか)、オプション料金の有無と金額、作業時間の目安、キャンセルポリシー、清掃不足の場合の保証などをしっかり確認しましょう。
業者選びは価格だけでなく、口コミや評判も参考にし、特に原状回復対応の経験が豊富かどうかも重要なポイントです。
自分で業者を手配する場合は事前に管理会社に確認し、見積もりは必ず書面で取得するようにしましょう。
依頼時期による料金の違い
ハウスクリーニング費用は、依頼する時期や条件によって大きく変動します。
特に注意すべきは繁忙期と閑散期の違いです。
3~4月や9~10月の引っ越しシーズンは業者の需要が集中するため、料金が10~20%程度高くなるのが一般的です。
また予約も取りにくくなりますので、早めの手配が必要です。
逆に6~7月や12~1月などの閑散期は割引キャンペーンが行われていることもあり、5~10%ほど安くなるケースがあります。
予約のタイミングも重要で、1ヶ月以上前に予約すれば基本料金で依頼できますが、2週間前だと若干の割増、3日前以内の緊急依頼では20~30%増しになることも少なくありません。
さらに作業希望日時によっても料金は変わります。
平日昼間(9時~17時)が最も安く、土日祝日は10~30%増、早朝・夜間対応だと20~50%増となる場合があります。
その他、荷物がある状態での清掃(入居中清掃)は20~30%増、エレベーターなしの5階以上の物件や駐車場がない場合も追加料金が発生します。
費用を抑えるためには、退去日が確定したらすぐに予約を入れる、可能であれば引っ越しシーズンを避ける、平日の日中に作業できるようスケジュールを調整するなどの工夫が効果的です。
敷金精算で損しない交渉術
退去時にクリーニング費用が敷金から差し引かれる場合、適正な費用負担を実現するために押さえておくべきポイントがあります。
まず敷金精算書が届いたら、詳細な内訳を必ず確認しましょう。
「クリーニング一式」などの曖昧な表現には詳細な内訳を要求し、相場と比較して高額な場合は根拠を確認することが重要です。
国土交通省のガイドラインでは通常損耗は貸主負担と定められており、特約がない限り、専門業者によるクリーニング費用全額を借主に負担させることは原則として認められていません。
また、壁紙などは経過年数(減価償却)によって借主負担額が大幅に減少します(壁紙は6年で価値がほぼゼロになる)。
交渉の際は、
「国交省ガイドラインでは通常損耗は貸主負担とされていますが、この汚れはどのように通常を超えていますか?」
「築○年の物件で、私は△年住んでいますが、経過年数は考慮されていますか?」
などと冷静に質問することが効果的です。
入居時・退去時の写真や動画、自分で取得した清掃業者の見積書なども有力な交渉材料になります。
交渉は段階的に進め、まずは電話やメールで質問し、納得できない場合は書面で正式に異議を申し立て、それでも解決しない場合は消費生活センターなどの第三者機関に相談しましょう。
敷金返還の具体的な流れとスケジュール
敷金がいくら戻ってくるのかは退去を控えた方にとって、とても大きな関心事です。
この章では、賃貸物件の退去後における敷金返還の手続きやタイミング、そして適正な返還額を確保するためのポイントについて紹介します。
敷金返還の具体的な流れとスケジュールには以下の内容があります。
- 退去時から敷金返還までの標準的な流れと各段階での注意点
- 敷金が返還されるまでの一般的な期間と返還遅延時の対処法
- 敷金精算明細書の見方と不当な控除を見抜くためのチェックポイント
退去から敷金返還までの手順
賃貸物件を退去してから敷金が返還されるまでには、いくつかの段階を経る必要があります。
まず最初は退去立会いです。
物件を完全に片付け、荷物を搬出した状態で、管理会社やオーナーの担当者と一緒に部屋の状態を確認します。
この時、壁や床の傷、水回りの状態、設備の動作確認などが行われます。
立会いには必ず借主本人が参加し、入居時の写真や契約書を持参すると安心です。
立会い終了後、鍵を返却し、退去完了です。
次は、管理会社が物件の最終確認を行い、修繕が必要な箇所を特定します。
この際、原状回復の範囲と責任の所在(貸主負担か借主負担か)が判断されます。
その後、実際に修繕工事やルームクリーニングが行われ、これには通常1~2週間程度かかるでしょう。
工事完了後、修繕費用が確定し、敷金からの控除額が計算されます。
ここでは経過年数(減価償却)も考慮されるべきです。
最後に、敷金精算明細書が作成され借主に送付され、差額が返金されます。
全体の流れを把握しておくことで、異常な遅延や不適切な対応に気づきやすくなるでしょう。
敷金はいつ頃返ってくる?
敷金が実際に返還されるタイミングは、一般的には退去後1~2ヶ月以内が目安です。
ただし、具体的な返還期間について法律で明確に定められた期限はなく、まずは自分の賃貸借契約書に記載がないか確認することが重要です。
契約書に「退去後30日以内に明細を送付する」「明細送付後10日以内に返金する」といった記載があれば、その期間が基準です。
敷金返還の手順は大きく分けて2つの期間があります。
まず退去日から精算書送付までは、修繕箇所の確認や工事・清掃の実施、費用の確定などの手続きが必要なため、通常2週間~1ヶ月程度かかります。
次に精算書受領から実際の返金までは、一般的に1~2週間程度です。
退去から1ヶ月経っても精算書が届かない場合や、精算書受領後2週間以上経っても返金がない場合は、管理会社に状況を確認してみましょう。
返還が著しく遅れる場合の対処法としては、まずメールや電話で催促し、それでも改善されなければ内容証明郵便で期限を区切って請求することも有効です。
問題が解決しない場合は、消費生活センターへの相談や少額訴訟の提起も検討できます。
敷金返還請求権の消滅時効は5年ですが、早めの対応が望ましいでしょう。
以下に敷金返還の一般的なスケジュールを表で示します。
|
手続き |
所要期間の目安 |
備考 |
|
退去立会い~明細書送付 |
2週間~1ヶ月 |
修繕箇所の確認、工事・清掃実施、費用確定が必要 |
|
明細書受領~実際の返金 |
1~2週間 |
契約書に期限の記載がある場合はそれに従う |
|
全体の流れ(退去~返金) |
1~2ヶ月 |
1ヶ月以上経過しても連絡がない場合は確認するとよい |
敷金精算明細書の確認点
敷金精算明細書が届いたら、すぐに内容を詳しく確認することが重要です。
まず各費用項目の内容と金額の妥当性をチェックしましょう。
「クリーニング費用一式」「修繕費用」などの曖昧な表現には具体的な内訳を求めてください。
1Kのハウスクリーニングが5万円など、相場と比較して明らかに高額な場合は要注意です。
次に、原状回復の負担区分が適切かどうかを確認します。
壁紙の変色や設備の経年劣化による故障は本来貸主負担であり、国土交通省の原状回復ガイドラインに照らして判断しましょう。
さらに、物件の経過年数(減価償却)が考慮されているか確認することも重要です。
例えば、壁紙やカーペット、エアコンなどの耐用年数は6年とされており、5年居住した場合、借主負担は残り1年分(約17%)のみとなるはずです。
壁紙張替えやカーペット交換の全額負担を求められた場合は、経過年数を考慮するよう交渉しましょう。
また、クリーニング特約に基づく請求があれば、契約時に具体的な説明と金額提示があったか思い出してください。
精算明細書に不明点や疑問があれば、遠慮せず管理会社に質問し、必要に応じて交渉することが大切です。
まとめ
賃貸物件の退去時におけるルームクリーニング費用は、原則として貸主負担が基本です。
国交省ガイドラインでは、通常使用による汚れや経年劣化はオーナー側が原状回復費用として負担すべきとされています。
ただし、契約書に特約がある場合は借主負担になることもありますが、その特約が有効となるには明確な説明と同意が必要です。
特約があっても通常使用による汚れは借主負担にできず、故意・過失による破損の場合のみ請求が認められます。
トラブル回避には入居・退去時の写真撮影や立会いが重要で、もし高額な請求で敷金返還に納得がいかないなど困ったときは消費者センターなどの相談窓口を活用しましょう。
«前へ「敷金トラブル回避!退去時の原状回復・ハウスクリーニング相場と対策」 | 「原状回復工事の業者選び|相場を知って安心できる優良業者を選ぼう!」次へ»