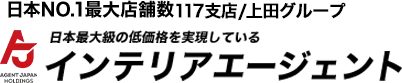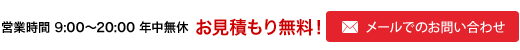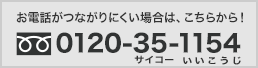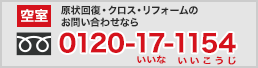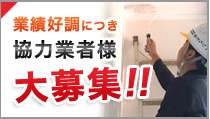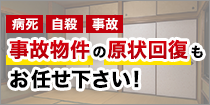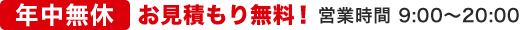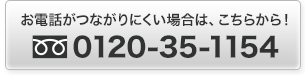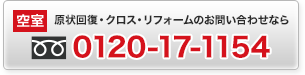原状回復費用は経費で落とせます!ケースで異なる勘定科目
原状回復とは、賃貸物件を借主(賃借人)が退去する時点で、物件を入居した際の状態に戻す工事のことを意味します。
故意もしくは通常の生活では生じないような汚れやキズがある場合を除いて、マンションやアパートといった個人向け賃貸住宅の場合、基本的には貸主(大家さん)が負担するのが一般的です。
しかし、オフィスや店舗などの場合、入居時に内装やレイアウト変更などを行うことが多いため、借主(賃借人)が負担するケースも多くあります。
原状回復を借主、貸主のどちらが行うかについては、賃貸契約書に記載されている内容をよく確かめましょう。
また、令和2(2020)年4月1日から施行されている改正民法では、賃借物件に経年劣化などによらない損傷が生じた場合は「賃借人の原状回復義務」が生じると規定されています。
目次
借主が原状回復費用を負担するケース
 オフィスや店舗などの賃貸物件の場合、例えば下記のような損傷は、借主が原状回復を負うケースが多いでしょう。
オフィスや店舗などの賃貸物件の場合、例えば下記のような損傷は、借主が原状回復を負うケースが多いでしょう。
- 引っ越しの際に生じた床や壁の傷
- 賃借人の不注意による床や壁の変色や色褪せ
- 喫煙による壁などのヤニや室内の臭い
- 壁に空いたクギ穴やネジ穴
- エアコンなどの水漏れによる壁の腐食
- パーテーション設置等による壁や床などの損傷…etc.
なお、借主が負担した現状回復費用は、経費として計上できます。勘定項目は支払い方法によっても異なりますので、以下にご説明しましょう。
一般的には勘定項目「修繕費」で仕訳
借主が現状回復費用を負担した場合、勘定科目は「修繕費」で経費計上するのが一般的です。
原状回復費用であることが明確でないと、修繕費として認められない場合がありますので、工事業者による見積書の項目には必ず「原状回復費用」と記載してもらいましょう。
オフィスや店舗の退去時に借主が原状回復工事を業者に依頼し、その費用50,000円を銀行口座から振り込みで支払った場合の仕訳例は以下となります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 修繕費 | 50,000円 | 普通預金 | 50,000円 | 原状回復費用 |
敷金や保証金から差し引かれた場合も「修繕費」で仕訳
入居前に敷金や保証金を貸主に預けている場合、原状回復費用を敷金や保証金から差し引かれるのが一般的です。
入居時に敷金400,000円を貸主に預け、原状回復費用80,000円が敷金から差し引かれ、残りの320,0000円が銀行口座に振り込まれた場合の仕訳例は以下の通りです。
▽入居時の仕訳
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 400,000円 | 普通預金 | 400,000円 | 敷金支払い |
▽退去時の仕訳
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 修繕費 | 80,000円 | 敷金 | 80,000円 | 原状回復費用 |
| 普通預金 | 320,000円 | 敷金 | 320,000円 | 敷金の返金 |
原状回復費用と保証金や敷金が同額ということは滅多にないでしょうが、敷金100,000万円から同額の原状回復費用が差し引かれているケースの仕訳例は以下となります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 修繕費 | 100,000円 | 敷金 | 100,000円 | 原状回復費用 |
「特別損失」として計上できる場合も
 特別損失とは、本来の事業活動で通常は発生しない、突発的・臨時的に発生する損失のことです。
特別損失とは、本来の事業活動で通常は発生しない、突発的・臨時的に発生する損失のことです。
したがって、原状回復費用が高額な場合、敷金を上回る場合、また減価償却が終わっていない入居時の内装工事なども「特別損失」になります。
特別損失には「経常利益が増加する」「節税になる」というメリットがありますが、毎年多額の特別損益が発生していれば信用リスクにも繋がりかねません。
原状回復費用を特別損失として経理処理するかどうかについては、あらかじめ税理士と相談することをおすすめします。
貸主(物件を貸した側の人または法人)が現状回復費用を負担するケース
 賃貸契約・特約の内容にもよりますが、以下のような賃貸物件の損傷については貸主(物件のオーナー)が原状回復を負担するのが一般的です。
賃貸契約・特約の内容にもよりますが、以下のような賃貸物件の損傷については貸主(物件のオーナー)が原状回復を負担するのが一般的です。
- 家具や什器の設置による床・カーペットの設置跡や凹み
- コピー機や冷蔵庫などの設置による壁の黒ずんだ電気焼け
- ポスターや額などを掲出した壁紙の変色・色落ち
- ピンや画びょうによる壁の小さな穴
- 賃貸人が設置したエアコンのビス穴などの設置跡
- 故障や使用不能になった冷暖房器具・給湯器・調理機器など
- 構造的な欠陥により生じた扉や襖のゆがみなど
- 畳の表替え・裏返し、網戸・サッシの交換、浴槽・風呂釜の交換、鍵の取り替え…etc.
一般的には勘定項目「立替金」で仕訳
貸主が原状回復費用を負担した場合、勘定項目は「立替金」です。
現金で原状回復費用を支払い、その金額が例えば60,000円だった場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 立替金 | 60,000円 | 現金 | 60,000円 | 原状回復費用 |
自己所有資産の修復と考えれば「修繕費」で仕訳
ただし、原状回復をオーナー自身が所有する資産の修復と考えれば、勘定科目は「修繕費」として仕訳することも可能です。
60,000円の原状回復費用を現金で支払い、修繕費として処理する場合の例は以下となります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 修繕費 | 60,000円 | 現金 | 60,000円 | 原状回復費用 |
敷金返還の際に差し引いた原状回復費用が「雑収入」になる場合もある
賃借人が入居した際に預かった敷金や保証金から立て替えた原状回復費用を差し引いて、残金を賃借人に払い戻すケースもあるでしょう。
ただし、「立替金」として処理するか、「修繕費」として処理するかで仕訳方法は異なります。
敷金が500,000円、現金で支払った原状回復費用が70,000円で、「立替金」として処理する場合は以下となります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 500,000円 | 現金 | 430,000円 | 敷金の返還 |
| 立替金 | 70,000円 | 原状回復費用 | ||
同じく敷金が500,000円、現金で支払った原状回復費用が70,000円でも、「修繕費」として処理する場合は「雑収入」となります。
なぜなら、修繕費は経費として扱う勘定科目ではないからです。そのため、「雑収入」として差し引き、以下のように仕訳します。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 500,000円 | 現金 | 430,000円 | 敷金の返還 |
| 雑収入 | 70,000円 | 原状回復費用 | ||
原状回復費用が節税になるケース
 コロナ渦でテレワークが普及し、オフィスを縮小する企業が増え、また、通販やデリバリーに特化した販売へと業態を変える店舗も増えてきました。
コロナ渦でテレワークが普及し、オフィスを縮小する企業が増え、また、通販やデリバリーに特化した販売へと業態を変える店舗も増えてきました。
それに伴い、旧オフィスや旧店舗から転出する際の賃借人が支払った「原状回復費用」は全額費用計上できます。つまり、経費として差し引けるので節税になります。
敷金や保証金から差し引かれた原状回復費用は全額計上できる
 賃借人が工事業者に直接支払った原状回復費用だけでなく、敷金や保証金から差し引かれた原状回復費用も、もちろん全額計上できます。
賃借人が工事業者に直接支払った原状回復費用だけでなく、敷金や保証金から差し引かれた原状回復費用も、もちろん全額計上できます。
一方、オーナーである賃貸人が現金で支払ったり、敷金や保証金から差し引いた原状回復費用も、非課税対応仕入れとなり、消費税は「立替金」や「修繕費」に含まれる非課税扱いとなります。
修繕費?資本的支出?迷った時に役立つフローチャート
原状回復費用を「修繕費」として計上できれば、支出金額を全額その年の経費とすることができます。
しかし、物理的に付け加えた部分の改良であったり、資産価値を高める改造や改装であったりすると、税務署から「資本的支出」に該当すると判断されてしまいます。
「資本的支出」に該当すると、資産計上を行って、数年かけて減価償却していくことになります。
「修繕費」か、「資本的支出」か迷ったら、以下のフローチャートを使って判断すると良いでしょう。
判断に迷った時に適用できる税金の特例もある
修繕費か資本的支出かが明らかでない原状回復費用に対して適用できる、以下のような税金の特例もあります。
資本的支出と修繕費の区分の特例
原状回復費用の支出が60万円以上で、しかも前期末取得価額×10%超であっても、継続適用を条件として、修繕費か資本的支出かが明らかでない金額を一定の割合で修繕費と資本的支出とに振り分けることができます。
災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例
法人が被災資産に対して支払った原状回復費用のうち、修繕費か資本的支出かが明らかでない金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とすることができます。
顧問税理士に一度相談されてみると良いでしょう。
オフィスや店舗などの原状回復費用に関するよくあるトラブル
退去時の原状回復を借り手と貸し手のどちらが行うのか、どの程度まで工事するのが妥当なのか、費用はどちらが負担すべきなのか…などは、しばしばトラブルになります。
特にオフィスや店舗などの場合、トラブルになりやすいのは以下のような点です。
- 敷金や保証金から差し引かれた原状回復費が適正価格かどうか。
- そもそもどこまでが原状回復なのか、適正な工事範囲が分からない。
- オフィスの通常損耗や自然損耗はどちらが負担すべきか。
- 借主負担による原状回復工事が明け渡し期日に間に合わず、遅延損害金を請求された。
- 民間住宅に対する国土交通省「原状回復ガイドライン」は、オフィスや店舗の賃貸物件にも適用できるのか。
国土交通省「原状回復ガイドライン」が示す基本のルール
 原状回復に関するトラブルを避けるには、入居時に交わした賃貸契約書に記載された原状回復に関する特約をよく確認し、お互いに納得のいく合意を得ておくことです。
原状回復に関するトラブルを避けるには、入居時に交わした賃貸契約書に記載された原状回復に関する特約をよく確認し、お互いに納得のいく合意を得ておくことです。
また、民間賃貸住宅の賃貸借契約におけるこうしたトラブルを避けるため、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」についてにまとめています。
さらに、このガイドラインを受けて民法が改正され、第621条に「賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について、原状回復の義務を負うが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない」旨が記されています。
原状回復に含まれる費用とは
 オフィスや店舗などの原状回復について、特にトラブルになりやすいのは「原状回復費が適正価格かどうか」「どこまでが原状回復工事の範囲なのか」「工事スケジュールが明け渡し期日までに間に合うのか」でしょう。
オフィスや店舗などの原状回復について、特にトラブルになりやすいのは「原状回復費が適正価格かどうか」「どこまでが原状回復工事の範囲なのか」「工事スケジュールが明け渡し期日までに間に合うのか」でしょう。
トラブルを未然に防ぐには、借主と貸主間で賃貸借契約書の原状回復に関する特約を再度確認し合い、さらに慎重を期すなら、工事前に見積を取って合意を得ることです。
原状回復費用の勘定項目と仕訳に関するまとめ
オフィスや店舗などの原状回復工事費用に関する、経理処理の主なポイントは以下となります。
- 借主が原状回復費用を負担する場合は、一般的には勘定項目「修繕費」で処理するが、「特別損失」として計上できる場合もある。
- 貸主が現状回復費用を負担する場合は、一般的には勘定項目「立替金」で処理するが、「修繕費」として処理し、「雑収入」になる場合もある。
- 「修繕費」は全額経費として計上することができるが、「資本的支出」に該当する場合は減価償却する必要がある。
- 「資本的支出」の税金に適用できる特例もある。
- 原状回復に関する借主・貸主間のトラブルを未然に防ぐには、工事前見積で合意を得ておくと良い。
お見積りのご依頼は、インテリアエージェントまでお気軽にどうぞ。
東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に年間8,000件以上の原状回復工事の実績がございます。
«前へ「原状回復工事とは?基礎知識から手順、費用相場まで徹底解説」 | 「原状回復の範囲はどこまで?マンションやオフィスの事例を解説」次へ»