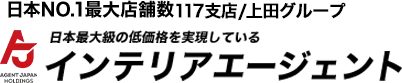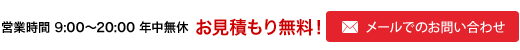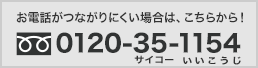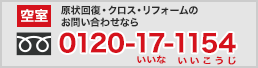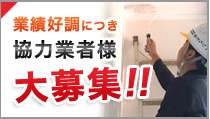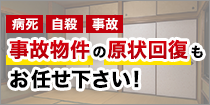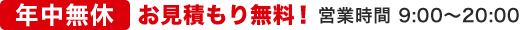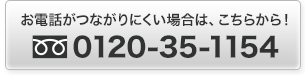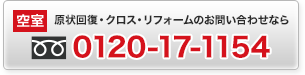テナントと居住用での原状回復に違いはある?費用や範囲・退去の段取りも紹介
テナントと居住用の原状回復の違い、正確に説明できますか?
住居用賃貸と同じ感覚で事業用テナント物件を契約すると、退去時に思わぬ高額な費用が発生する恐れがあります。
この記事では、事業用のテナントと居住用物件の原状回復の違いを具体例とともに分かりやすく解説し、退去費用の相場や抑え方、契約書の注意点まで詳しく紹介します。
読み終える頃には、トラブルを回避し、安心して事業を進めるためのヒントが得られるでしょう。
目次
テナントと居住用の原状回復とは?
事業用のテナント物件と、私たちが普段住むための居住用物件では、「原状回復」の考え方や範囲が大きく異なります。
この章では、テナントと居住用物件の原状回復の基本的な考え方とその違いについて紹介します。
原状回復について、この章で取り上げる主な内容は以下のとおりです。
- 原状回復の正確な定義
- テナント物件の原状回復の特徴
- 居住用物件の原状回復の特徴
- 違いを理解する重要性
ポイント(1)原状回復の正確な定義
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、入居時の状態に戻す義務のことです。
しかし、この「入居時の状態」の解釈が、物件の種類や契約内容によって大きく変わる点に注意が必要です。
例えば、一般的な居住用物件では、日常生活で生じる自然な経年劣化や通常の使用による損耗、例えば壁紙の日焼けなどについては、原則として貸主の負担です。
借主が負担するのは、自身の故意や過失によって生じさせた損傷、例えば壁に穴を開けた、設備を壊したなどが中心です。
一方、事業用テナント物件では、契約書の定めが優先され、経年劣化や通常損耗を含めて借主が費用を負担するケースが多く見られます。
この違いを認識し、契約書で原状回復の範囲を明確に定めておくことが、後のトラブルを防ぐ上で極めて重要になります。
ポイント(2)テナント物件の原状回復
テナント物件における原状回復は、契約書に記載された条件が最も優先されるルールです。
事務所や店舗といった事業用物件では、「スケルトン戻し」といって、借主が設置した内装や設備をすべて撤去し、建物の骨組みだけの状態に戻すことを求められるケースが一般的です。
この場合、工事費用は原則として全額借主の負担です。
特に、飲食店などでは厨房設備や大掛かりな排気ダクトの撤去が伴うため、オフィスや小売店と比較して原状回復費用が高額になる傾向があります。
そのため、契約を締結する前に、貸主指定の工事業者の有無や、原状回復義務を一部免除する特約(免責特約)の交渉可能性などを確認し、将来的な費用負担を軽減する工夫が求められます。
ポイント(3)居住用物件の原状回復
居住用物件の原状回復は、国土交通省が定めたガイドラインに基づいて判断されます。
このガイドラインによれば、壁紙の日焼けや画鋲の跡、家具の設置による床のへこみなど、通常の住まい方で自然に発生する経年劣化や損耗については、基本的に貸主の負担とされています。
借主が費用を負担するのは、タバコのヤニによる著しい汚れや臭い、ペットによる柱の傷、不注意で破損させた設備など、故意・過失や通常とは言えない使用方法による損傷が主な対象です。
したがって、居住用物件を借りる際は、このガイドラインの内容を理解した上で契約条件を確認し、退去時の費用負担についてあらかじめ見通しを立てておくと、安心して生活を送ることができます。
ポイント(4)違いを理解する重要性
テナント物件と居住用物件とでは、このように原状回復の考え方が根本的に異なります。
この違いを正確に認識しておくことは、退去時に想定外の高額請求を受けたり、貸主との間で深刻なトラブルに発展したりするリスクを避けるために、極めて重要です。
特に、居住用物件の経験しかない方が同じような感覚でテナント契約を結んでしまうと、退去時に「こんなはずではなかった」と大規模な内装解体や設備撤去費用に直面し、事業の継続に支障をきたすケースも少なくありません。
契約内容を隅々まで確認し、事前に複数の業者から見積もりを取得して費用を把握すればスムーズに退去できコスト削減にもなります。
加えて、近年では不当に高額な原状回復費用の請求に対して、裁判所が借主保護の判断を示す判例も見られるため、基本的な法的知識を身につけておくことも、自身を守る有効な手段と言えるでしょう。
原状回復範囲はどこまで必要?
原状回復の範囲を正しく理解しているかどうかで、退去時の費用負担や手間が大きく変わってきます。
この章では、居住用とテナント物件における原状回復の範囲について紹介します。
原状回復の範囲を理解することで、退去時のトラブルを防ぎ、コスト削減につなげることができます。
主な内容として以下を取り上げます。
- 居住用物件の原状回復範囲の基準
- テナント物件での契約書の重要性
- スケルトン戻しを求められるケース
- 民法改正が原状回復に与えた影響
範囲(1)居住用:国の指針が基準
居住用物件の場合、原状回復の範囲を判断する上で最も重要な基準となるのが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
この指針に基づき、例えば冷蔵庫裏の壁紙の電気焼け、日光による畳やフローリングの色褪せ、通常使用による家具の設置跡といった「経年劣化」や「通常損耗」と判断されるものは、原則として貸主の費用負担で修繕されることになります。
反対に、借主が負担すべき範囲としては、喫煙による壁紙の広範囲なヤニ汚れ、結露を放置したことによるカビやシミ、ペットがつけた柱や壁の傷などが挙げられます。
このガイドラインの存在により、貸主と借主双方の負担区分がある程度明確化され、退去時の紛争防止に役立っています。
範囲(2)テナント:契約書が最優先
一方、テナント物件の原状回復範囲においては、居住用のガイドラインは原則として適用されません。
ここで絶対的な効力を持つのが、貸主と借主の間で交わされる「賃貸借契約書」です。
したがって、事務所や店舗などの事業用物件を契約する際には、契約書の条項一つひとつを細心の注意を払って確認する必要があります。
特に注意したいのが、内装や設備をすべて撤去して建物の躯体だけの状態に戻す「スケルトン戻し」の義務が定められているケースです。
これを居住用物件と同じような感覚で捉えていると、退去時に莫大な原状回復費用を請求されかねません。
契約締結前に、原状回復の範囲や費用負担を少しでも軽減できるような特約を盛り込む交渉が、将来の紛争を避けるために不可欠です。
範囲(3)スケルトン戻しの要求度
テナント物件、特に店舗やオフィスでは「スケルトン戻し」を契約条件として求められることが頻繁にあります。
これは、借主が事業活動のために設置した壁、床、天井の仕上げなどの内装や、空調、照明、間仕切り、厨房設備などの各種設備をすべて解体・撤去し、建物のコンクリート躯体や骨組みがあらわになった状態、つまりスケルトン状態にして返還することです。
飲食店であれば、大型の厨房機器や複雑な排気・給排水設備の撤去が必要となるため、工事費用は特に高額になります。
貸主がスケルトン戻しを要求する主な理由は、次の入居者が業種や内装デザインの制約を受けずに、自由にプランニングできるようにするためです。
したがって、テナント契約を結ぶ前には、契約書でスケルトン戻しの義務があるのか、あるとすればどこまでの範囲を指すのかを明確に確認し、概算でも良いので事前に専門業者に費用の見積もりを取っておくことが、後の資金計画において非常に重要です。
範囲(4)民法改正による影響範囲
2020年4月に施行された改正民法では、賃貸借契約における原状回復に関するルールがより明確にされました。
具体的には、借りた物件である賃借物に生じた損傷のうち、借りた人の責任ではない原因で生じたもの、例えば通常の使用や経年変化によって生じる損耗については、賃借人は原状回復義務を負わない、という点が明文化されたのです。
これは主に居住用物件を念頭に置いた改正ですが、テナント物件であっても、この民法の原則が全く無関係というわけではありません。
ただし、テナント契約においては、当事者間の合意、つまり契約書の特約が民法の規定に優先して適用されるのが実情です。
その結果、特約によって経年劣化や通常損耗分についても借主の負担とする契約が依然として多くみられます。
したがって、契約締結時には、改正民法の趣旨を理解した上で、あまりにも借主に一方的に不利な特約、例えば全ての損耗を借主負担とするような条項が含まれていないかを確認し、必要であれば貸主側と協議し、より公平で合理的な内容に修正する交渉を試みましょう。
テナント原状回復費用はどれくらい?
テナント物件の退去時に最も気になるのが、原状回復にかかる「費用」ではないでしょうか。
この章では、テナント物件における原状回復の費用について詳しく解説します。
テナントの場合、居住用物件と比較して費用が高額になる傾向があり、その理由と具体的な費用相場を知ることで、予算計画やコスト削減に役立てることができます。
主な内容として以下を取り上げます。
- テナントの原状回復が高額な理由
- 原状回復費用の具体的な内訳
- 業種ごとの坪単価の相場
- 原状回復費用を削減する交渉術
費用(1)テナント費用が高額な理由
テナントの原状回復費用が高額になる主な理由は、スケルトン戻しといわれる内装や設備の完全撤去が求められることが多いからです。
居住用であれば、通常損耗部分の補修やクリーニング程度で済む場合がほとんどですが、テナント物件、特に事業用にカスタマイズされた内装や設備を持つ場合は、それらを全て撤去し、入居前の何もないスケルトン状態に戻すことが求められます。
例えば、飲食店であれば厨房設備一式、オフィスであれば造作した会議室の間仕切りや専用の空調・電気設備などが対象となり、これらの解体・撤去工事だけでも相当な費用が発生します。
さらに、解体に伴って発生する大量の産業廃棄物の適正な処理費用も加わるため、最終的な請求額が当初の予想を大きく上回ることも少なくありません。
費用(2)主な費用の内訳
テナントの原状回復費用は主に以下のような項目で構成されています。
| 費用項目 | 主な内容 |
| 内装解体工事費 | 借主が設置した内装材(壁紙、床材、天井材など)や間仕切り壁などの解体・撤去 |
| 設備撤去工事費 | エアコン、照明器具、厨房設備、店舗什器といった各種設備の撤去 |
| 電気 給排水設備工事費 |
不要になった電気配線やLANケーブル、給排水管の撤去や閉鎖処理 |
| 産業廃棄物処理費 | これらの工事から発生する廃材を法律に則って処分するための費用(種類や量で変動) |
| 清掃 クリーニング費 |
工事完了後の清掃作業 |
| 最終検査立会い費用など | 場合によっては、貸主や管理会社との最終検査立会いにかかる費用などが加算される |
これらの各費用項目は、物件の広さ、業種、設置されている設備の量や種類、解体の難易度、選択する工事業者などによって大きく変動します。
特に、産業廃棄物処理費は、廃棄物の種類や量、処分方法によって高額になることがあります。
退去前には必ず複数の専門業者から詳細な見積もりを取得し、それぞれの項目の内容を契約書と照らし合わせながら吟味することが、予期せぬ高額請求を避けるために非常に重要です。
不明な点は遠慮なく業者や貸主に確認しましょう。
費用(3)坪単価で見る費用相場
テナントの原状回復費用を坪単価で見た場合、物件の規模や立地、そして何よりも業種と内装・設備の状況によって大きく変動します。
あくまで一般的な目安ですが、比較的内装がシンプルなオフィスの場合、1坪あたり2万円~5万円程度が相場と言われています。
アパレルや雑貨などの小売店舗、美容室やエステサロンなどでは、坪あたり3万円~8万円程度を見込むとよいでしょう。
一方で、厨房設備や専用の排気・給排水設備、重厚な内装を伴うことが多い飲食店の場合、坪単価は5万円~10万円以上、場合によってはそれ以上になることもあります。
特に、油汚れの洗浄や大掛かりなダクト撤去が必要となる焼肉店、中華料理店、ラーメン店などの「重飲食店」と呼ばれる業態では、坪あたり10万円を大きく超えるケースも珍しくありません。
このように、ご自身の事業の業態や導入した設備の規模によって費用相場が大きく異なることを、あらかじめ理解しておくことが重要です。
以下に粒単価で見る費用の目安を表で示します。
| 業種 | 坪単価の目安 |
| オフィス (内装がシンプルな場合) |
2万円~5万円程度 |
| 小売店舗 (アパレル、雑貨など) |
3万円~8万円程度 |
| 美容室、エステサロン | 3万円~8万円程度 |
| 飲食店 (一般) |
5万円~10万円以上 |
| 飲食店 (焼肉店、中華料理店など) |
10万円を大きく 超えることも |
費用(4)賢い費用削減の交渉術
高額になりがちなテナントの原状回復費用ですが、いくつかのポイントを押さえることで賢く削減できる可能性があります。
最も効果的なのは、やはり契約締結前の「交渉」です。
具体的には、退去時の原状回復義務の範囲について、現状有姿(現状のまま)での返却や、造作や設備を後継テナントに引き継ぐ、居抜きでの退去を認めてもらうよう、貸主側と粘り強く交渉してみましょう。
また、契約書に「貸主指定業者」による工事が義務付けられている場合でも、その条項の削除や緩和を求め、複数の専門業者から相見積もりを取れるようにすることも、コスト競争を生み費用削減に繋がる重要なテクニックです。
その他、DIYで対応可能な範囲の簡易な撤去作業を自分たちで行う、あるいは費用対効果の高いテナント専門の解体業者を自ら探して依頼するといった方法も有効でしょう。
これらの交渉や工夫を事前に行うか否かで、最終的な費用負担が大きく変わってくる可能性があります。
退去・明け渡しの段取りは?
テナント物件の退去を決めた後、実際に物件を明け渡すまでには、いくつかの重要な手続きを経る必要があります。
この章では、テナント物件の退去から明け渡しまでの具体的な流れについて紹介します。
事業用物件の退去は準備が不十分だと高額な費用やトラブルに繋がるため、適切な段取りが必要です。
主に以下の内容があります。
- 解約予告から工事着工までの流れ
- 工事完了後に行う明け渡し検査
- 鍵返却から敷金精算までの手順
段取り(1)解約予告から工事着工まで
テナント物件から退去する場合、まず最初に行うべきは、賃貸借契約書で定められた予告期間に従って、貸主か管理会社へ「解約予告」を通知することです。
一般的には、契約終了を希望する日の3ヶ月~6ヶ月前までに書面で通知するよう定められています。
解約予告と並行して、契約書を改めて隅々まで確認し、原状回復義務の範囲と、必要な工事の具体的な内容を正確に把握しましょう。
この段階で、複数の原状回復専門業者に現地調査を依頼し、見積もりを取得します。
少なくとも2~3社から相見積もりを取り、工事内容と費用を比較検討することで、適正価格での発注やコスト削減が期待できます。
業者を選定する際には、見積金額だけでなく、実績や担当者の対応なども含めて総合的に判断し、内装や設備の撤去範囲について認識の齟齬がないよう、明確に伝えることが後のトラブル防止に繋がるでしょう。
業者決定後は、速やかに工事契約を結び、退去日から逆算して無理のない工事スケジュールを組むことで、余裕を持った明け渡し準備を進められます。
段取り(2)工事完了と明け渡し検査
原状回復工事が無事完了したら、次に行うのが貸主の立ち会いのもとで行われる「明け渡し検査」です。
この検査は、契約書で定められた通りの範囲で原状回復工事が適切に実施され、施工品質に問題がないかなどを最終確認するため非常に重要です。
多くの場合、貸主、借主、そして実際に工事を担当した施工業者の三者が現地に揃い、事前に取り交わした仕様書やチェックリスト、工事前後の写真などを用いながら、物件の隅々まで細かく確認作業を行います。
この時点で貸主側から修繕不備や契約内容との相違点を指摘されると、追加工事が必要になったり、その費用負担を巡ってトラブルになったりする可能性があるため、検査には細心の注意を払う必要があります。
無用なトラブルを避けるためにも、契約内容や工事に関する合意事項を再度確認し、検査結果については双方が納得した上で、その内容を書面に記録として残しておきましょう。
段取り(3)鍵返却と敷金精算の流れ
明け渡し検査で問題なしと判断されれば、いよいよ物件の「鍵の返却」と「敷金の精算」手続きへと進みます。
鍵の返却は、原則として賃貸借契約の終了日に行います。
ただし、検査で修繕指示が出た場合は、その是正工事が完了し再検査で承認を得た後になることもあります。
鍵を貸主に返却した時点で、正式に物件の明け渡しが完了したとみなされ、その後、貸主側で敷金の精算処理が開始されます。
敷金からは、契約に基づいて借主が負担すべき原状回復費用や、未払い賃料などがあればそれらが差し引かれ、残額が返還される流れです。
貸主から提示された精算書の内容、特に原状回復費用の請求額については、事前に業者から取得した見積もりや工事内容と照らし合わせ、不当な請求や不明瞭な点がないかをしっかりと確認することが必要です。
万が一、納得のいかない項目があれば、速やかに貸主に説明を求め、話し合いによって解決を図りましょう。
一般的には、明け渡しから1~2ヶ月程度で敷金精算が完了することを目指します。
原状回復工事で失敗しないための注意点
原状回復をできる限りスムーズに進め、予期せぬトラブルや追加費用を避けるためには、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。
この章では、原状回復工事を進める際にトラブルや余計な費用の発生を防ぐための注意点を紹介します。
原状回復工事を円滑に進めるためには以下のポイントを押さえることが重要です。
- 工事着手前に準備すべき内容の確認
- 業者を選ぶ際のポイント
- 居抜き物件特有の注意事項
- 自分で増設した設備の扱い方
注意点(1)工事着手前の準備事項
原状回復工事をスムーズに進めるためには、工事開始前にしっかりと準備を行うことが重要です。
最も重要なのは、賃貸借契約書に記載されている「原状回復義務の範囲」と「特約条項」を改めて徹底的に確認することです。
例えば、スケルトン戻しが原則と定められているのか、一部造作・設備の残置が可能なのか、あるいは通常損耗も借主負担といった特約が付いているのかなど、契約書には工事の進め方や費用負担を左右する重要な情報が詳細に記載されています。
これらの条項を見落としたり、曖昧な解釈のまま進めてしまったりすると、工事完了後に貸主から契約違反を指摘され、追加工事や違約金の支払いが発生する、といった深刻なトラブルに繋がりかねません。
したがって、契約書の内容を細部まで精査し、不明な点や疑問点は必ず事前に貸主や管理会社に確認を取り、工事範囲や条件について双方で明確な合意を書面などで形成しておくことが不可欠です。
注意点(2)信頼できる業者の選び方
原状回復工事の品質と費用を大きく左右するのが工事業者選びです。
テナント物件の原状回復は、居住用物件のリフォームとは異なり、店舗やオフィス特有の複雑な設備の解体・撤去ノウハウ、さらには産業廃棄物の適切な処理知識が求められます。
そのため、安易に価格だけで選んだり、居住用専門の業者に依頼したりすると、施工不良や手戻り工事が発生し、かえって費用と時間がかさむリスクがあります。
信頼できる業者を選ぶためには、必ず複数のテナント専門業者から相見積もりを取り、提示された金額だけでなく、過去の施工実績、見積内容の詳細さ、担当者の専門知識や対応の丁寧さなどを総合的に比較検討することが重要です。
また、前述の通り、もし契約書に貸主指定業者の条項がある場合は、その撤廃や、少なくとも複数業者からの見積もり取得を認めてもらうよう交渉することも、適正価格での工事実現に向けた大切なポイントです。
注意点(3)居抜き物件の原状回復
居抜き物件の原状回復は、特に注意が必要です。入居時に居抜きで借りたからといって、退去時も同様に居抜きで明け渡せるとは限りません。
必ず賃貸借契約書で、退去時の原状回復義務がどのように定められているかを詳細に確認する必要があります。
もし、居抜き退去可の特約があったとしても、残置する設備の範囲や状態について貸主との間で明確な合意がなければ、後々トラブルになりかねません。
例えば、貸主が次のテナントに同業種での利用を期待していたとしても、残置された設備があまりにも老朽化していたり、衛生状態が悪かったりすれば、結局借主の費用負担で撤去や修繕を求められるケースもあります。
したがって、居抜き物件の場合でも、入居時の契約内容の確認はもちろん、退去が具体的に決まった段階で改めて貸主と協議し、残置できるものと撤去すべきものを明確にし、書面で合意しておくことが、予期せぬ費用発生を防ぐために極めて重要です。
注意点(4)増設した設備の扱い方
賃貸期間中に、借主が自身の事業運営のために新たに取り付けたり、増設したりした設備や内装については、原則として退去時に借主の責任と費用負担で撤去し、入居時の状態に戻す義務があります。
これを収去義務と呼びます。
契約書に、造作買取請求権の放棄といった条項が含まれている場合、これらの増設物を貸主に買い取ってもらうこともできません。
もし、これらの設備を残したまま無断で退去してしまうと、後日、貸主側が専門業者に依頼して撤去作業を行い、その実費に加えて遅延損害金などを請求される可能性があります。
そうした事態を避けるためにも、退去の意思を伝えた後、なるべく早い段階で貸主と協議の場を設け、どの設備を撤去し、どの設備であれば残置できるのか、その範囲を明確に確認しましょう。
その内容を原状回復工事の計画に漏れなく盛り込むことが、無用なトラブルと追加費用を避ける上で非常に大切です。
原状回復トラブルを防ぐには?
テナントの原状回復は、残念ながら貸主と借主の間でトラブルが発生しやすい場面の一つです。
この章では、原状回復工事を行う際に起こりやすいトラブルとその防止方法について紹介します。
トラブルを避けるためには、以下のポイントを事前に押さえておくことが重要です。
- よくあるトラブルの具体例の把握
- 貸主と借主の認識のズレを防ぐ工夫
- 契約時に確認すべき重要ポイント
- 専門家のアドバイスを活用する方法
トラブル(1)頻発するトラブル事例
テナントの原状回復において最も頻繁に発生するのが、費用負担の範囲を巡るトラブルです。
具体的には、「この傷は通常損耗なのか、それとも借主の過失によるものなのか?」といった経年劣化や通常損耗の解釈の違いによる争いが後を絶ちません。
居住用であればガイドラインが一定の基準を示しますが、テナントの場合は契約書の特約次第で、通常損耗分まで借主負担とされることが少なくありません。
また、「原状回復工事は貸主が指定する業者に依頼しなければならない」という契約条項があり、相場よりも明らかに高額な見積もりを提示され、断れずにやむなく受け入れてしまうケースも散見されます。
さらに、退去後の敷金精算で、覚えのない工事費用や過大な修繕費が一方的に差し引かれてしまうといった金銭トラブルも典型例です。
これらの問題を未然に防ぐためには、やはり契約締結の段階で、費用負担の原則、原状回復の具体的な範囲、工事の進め方などについて、貸主側と徹底的に協議し、その内容を明確に書面で合意しておくことが最も重要です。
トラブル(2)貸主との認識ズレを防ぐ
原状回復に関するトラブルの根源をたどると、その多くが貸主と借主の間にある認識のズレや期待値の不一致に行き着きます。
例えば、借主側は「この間仕切り壁は次のテナントも使えるだろうから、好意で残しておこう」と考えていても、貸主側は「契約通りスケルトンに戻してもらうのが当然」と捉えているかもしれません。
こうした些細な思い込みや確認不足が、退去間際になって表面化し、工事のやり直し、想定外の追加費用負担、最悪の場合は明け渡し遅延による損害賠償請求といった深刻な事態に発展する可能性があります。
このような認識のズレを防ぐためには、まず契約締結時に原状回復の範囲や条件を曖昧なままにせず、具体的に文書化しておくことが大前提です。
そして、退去が決まった際には、改めて貸主や管理会社と打ち合わせの機会を設け、どの部分をどのように修繕・撤去するのか、写真や図面なども活用しながら、双方の認識を細部まで丁寧にすり合わせ、合意内容を議事録などの形で記録しておくことが、後の「言った・言わない」のトラブルを避ける上で極めて有効です。
トラブル(3)契約時の詳細確認
テナント契約におけるトラブル予防の最大の鍵は、何と言っても「契約書」の内容を契約締結前に徹底的に精査することです。
特に原状回復に関する条項は、一言一句見逃さずに確認する必要があります。
契約書上で以下の内容を明確に確認しなければなりません。
- 原状回復の範囲はどこまでか
- 通常損耗や経年劣化の扱いはどうなるのか
- 原状回復工事の業者は貸主指定か、借主が自由に選べるのか
- 敷金から原状回復費用を差し引く際の具体的な手続きや精算方法は何か
これらの記載が曖昧であったり、解釈の余地が大きい表現が使われていたりすると、退去時に貸主側の一方的な解釈で高額な費用を請求されるなど、不利な状況に立たされるリスクが高まります。
契約書の内容に少しでも疑問や不安を感じたら、決して安易に署名・捺印せず、不動産取引に詳しい行政書士や弁護士などの専門家に相談し、リーガルチェックを受けることを強くお勧めします。
専門家の視点から不利益な条項やリスクの高い箇所を指摘してもらい、必要であれば契約締結前に貸主側と交渉して修正を求めることが、将来の紛争を回避する最善策の一つです。
トラブル(4)専門家相談の有効活用
もし原状回復に関する契約内容の解釈や、実際の工事の進め方、あるいは貸主との交渉などで少しでも不安や疑問を感じたら、一人で抱え込まずに専門家の知見を積極的に活用しましょう。
原状回復のルールは、民法や借地借家法といった法律の知識に加え、過去の判例や業界慣行など、専門的な理解が求められる領域です。
そのため、借主自身が十分な情報を持たないまま判断したり交渉したりすると、不利な条件を飲まされたり、トラブルがより複雑化したりする恐れがあります。
具体的には、契約締結前であれば、弁護士や不動産に強い行政書士に契約書のリーガルチェックを依頼することで、潜在的なリスクや不公平な条項を事前に発見し、修正交渉のアドバイスを受けることができます。
また、実際に原状回復工事の段階で貸主と意見が対立してしまった場合や、不当に高額な費用を請求されたといったトラブルが発生した際には、弁護士に代理交渉を依頼に相談したりすることも有効な解決手段となり得ます。
早期に専門家に相談することで、問題が大きくなる前に対処でき、時間的・金銭的な損失を最小限に抑えることが期待できるでしょう。
契約前にチェックすべき重要ポイント
テナント契約は、一度締結するとその内容に法的に拘束される重要な取り決めです。
この章では、テナント契約を締結する前に特に確認しておくべきポイントを紹介します。
契約内容を詳細に把握することで、退去時のトラブルや想定外の費用発生を避けることができます。
主に以下の内容があります。
- 契約書の確認すべき重要な箇所
- 特約条項で気をつけるべき点
- 原状回復義務の範囲確認の方法
- 指定業者の有無と影響
チェック(1)契約書で見るべき箇所
テナント契約書をチェックする際、まず最優先で確認すべきは、原状回復義務の範囲と費用負担の原則に関する条項です。
具体的には、どこまでを入居時の状態とみなし、何をどこまで復旧する必要があるのかが明確に定義されているかを確認します。
特にスケルトン戻しが義務付けられている契約では、借主が設置した内装や設備を全て撤去し、建物の躯体(構造体)のみの状態に戻す必要があるため、工事範囲が広大となり、必然的に高額な費用が発生する可能性を覚悟しなければなりません。
もし契約書を読んでも、具体的な撤去範囲や工事の仕様が不明確な場合は、決してそのままにせず、必ず契約前に貸主や仲介業者に質問し、必要であれば覚書や特約といった形で書面に明記してもらうように交渉しましょう。
曖昧な理解のまま契約を進めてしまうと、退去時に貸主との間で解釈の違いが生じ、深刻なトラブルに発展する最大の原因となります。
チェック(2)特約条項の徹底確認
契約書に記載されている特約条項は特に注意して確認すべきポイントです。
テナント物件の契約では、民法や借地借家法の原則的なルールよりも、この特約条項の内容が優先されるケースが非常に多いため、原状回復の範囲や費用負担に関する取り決めが、借主にとって有利にも不利にも大きく左右される可能性があります。
例えば、「契約期間が5年以上の場合は、通常損耗に関する原状回復義務を免除する」といった借主側にメリットのある特約です。
逆に「通常損耗や経年劣化も含め、一切の修繕費用は借主の負担とする」といった、民法の原則よりも借主に重い責任を課す不利な特約も存在します。
これらの特約は、一度合意してしまうと後から変更することは極めて困難です。
したがって、契約書に署名する前に、一つひとつの特約条項の意味内容を正確に理解し、少しでも不明な点や納得できない点があれば、安易に受け入れずに貸主側と交渉し、修正を試みることが不可欠です。
必要であれば、前述の通り専門家の意見も聞きながら慎重に判断しましょう。
チェック(3)退去時の義務範囲の特定
退去時に負うことになる原状回復義務の具体的な範囲を、契約締結の段階でどこまで明確に特定できるかが、後のトラブルを回避する上で極めて重要になります。
例えば、飲食店を経営する予定であれば、自ら設置する厨房設備や造作したカウンター、取り付けた看板などが撤去対象となるのかを検討します。
あるいはオフィスであれば、独自に敷設したOAフロア、造作した会議室のパーテーション、増設した空調機などが原状回復の範囲に含まれるのかなど、ご自身の事業計画と照らし合わせて具体的に想定し、確認する必要があります。
これらの点を曖昧なまま契約してしまうと、いざ退去する段になって「これは撤去対象外だと思っていた」「ここまで求められるとは聞いていない」といった貸主との認識の齟齬が生じ、予期せぬ追加工事や高額な費用負担が発生するリスクがあります。
理想は、契約書本文や添付される仕様書、あるいは別途覚書といった形で、撤去すべきもの・残置してよいものをリスト化するなど、具体的な工事範囲を明文化し、貸主・借主双方が納得の上で合意しておくことです。
これにより、退去時の無用な紛争を大幅に減らすことができます。
チェック(4)指定業者の有無を確認
契約時に確認すべき重要な項目の一つが「指定業者」の存在です。
これは、貸主が「原状回復工事は、当方が指定するA社に行わせるものとする」といった形で、工事を特定の業者に発注することを借主に義務付ける条項です。
もしこのような条項があると、借主は他の業者に相見積もりを取って費用を比較検討したり、より安価で質の高い業者を選んだりする自由が奪われ、結果的に貸主指定業者の提示する高額な工事費用を受け入れざるを得なくなるリスクがあります。
適正な競争原理が働かないため、工事費用が相場よりも割高になるケースが少なくありません。
したがって、契約書に指定業者条項が含まれている場合には、可能であれば契約締結前に貸主と交渉し、この条項自体の削除を求めるか、少なくとも「借主が選定した複数の業者からも見積もりを取得し、貸主指定業者と比較検討することを認める」といった内容に修正してもらうなど、費用抑制のための対策を講じておくことが強く推奨されます。
これにより、不必要なコスト負担を回避できる可能性が高まります。
まとめ
テナント物件と居住用物件の原状回復では、契約上の取り決めが大きく異なります。
テナント物件の場合、居住用とは異なり契約書が最優先され、特約条項により負担範囲が明確化されます。
スケルトン返しの義務や指定業者の有無など、退去時のトラブルを避けるには、契約前に詳細な確認と専門家への相談が重要です。
また、原状回復工事の見積もりを複数業者から取得し、相場を把握することで高額な請求を防げます。
費用面や工事の段取りも事前に理解し、スムーズな移転や退去を目指しましょう。
«前へ「原状回復の見積もり、その費用は適正?正しい内訳を知って損しない金額の計算方法を知ろう!」 | 「【保存版】賃貸の原状回復義務まるわかりガイド|入居から退去まで」次へ»