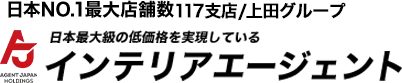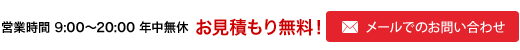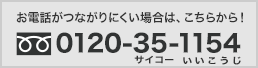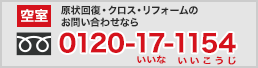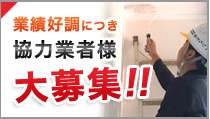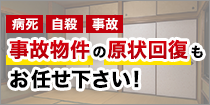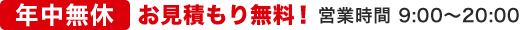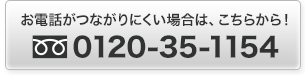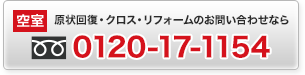原状回復とスケルトン、違いと費用を3分解説!
原状回復とスケルトン戻しの違いが分からず、退去時の費用や段取りに不安を感じていませんか?
この記事を読めば、原状回復とスケルトンの定義やどこまでの内装や設備の撤去が必要となるかといった具体的な工事範囲が明確になり、費用を抑えてスムーズに退去する方法が分かります。
特に飲食店などの業種では、厨房設備の撤去など工事範囲が大きく変わるため、その違いを理解することが重要です。
工事の相場や見積もりのポイントや居抜きでの退去も視野に入れた貸主との交渉術まで詳しく解説します。
トラブルなく安心して次のステップへ進みましょう。
目次
スケルトン戻しと原状回復の違い
この章では、「スケルトン戻し」と「原状回復」の違いをわかりやすく解説します。
両者の違いは以下の4つです。
- コンクリート打ちっぱなしの状態(スケルトン)
- 入居時の状態に戻す(原状回復)
- 契約書による回復範囲の違い
- 契約書の原状回復条項の重要性
スケルトン戻しと原状回復の違い
|
項目 |
スケルトン戻し |
原状回復 |
|
定義 |
内装や設備をすべて撤去し、コンクリートや躯体が露出した状態に戻す |
借りた入居時の状態に戻す |
|
工事範囲 |
床材、天井材、壁材、電気配線、空調設備、給排水設備などすべて撤去 |
入居後に借主が設置した間仕切り、棚、照明器具など |
|
費用負担 |
一般的に高額(坪3万〜10万円) |
スケルトン戻しより低額 |
|
適用条件 |
契約書に明記されている場合や貸主から指示がある場合 |
借地借家法の原則、特約がなければこちらが基本 |
|
飲食店の場合 |
内装設備の複雑さにより工事範囲が広く、費用も高額 |
居抜き物件であれば既存設備の撤去は不要 |
コンクリート打ちっぱなしの状態
スケルトン戻しとは、建物の内装や設備をすべて撤去し、コンクリートや躯体(建物の骨組み)が露出した状態に戻す工事のことをいいます。
特に飲食店や店舗では、内装設備が複雑で多岐にわたるため、工事範囲が広く、撤去費用も高額になる傾向があります。
具体的には、床材や天井材を完全に取り除き、電気配線や空調設備、給排水設備の配管まで撤去するケースが一般的です。
物件を借りた時点で内装がなく「スケルトン状態」であった場合、退去時にもスケルトン戻しをする必要があり、費用負担が重くなります。
貸主側が次のテナントの自由な設計を可能にするために求める工事であり、通常は契約書にも明確に記載されています。
トラブル回避には、事前に貸主と範囲の合意をとり、詳細な見積もりを取得して費用面での不安を解消しておくことが重要です。
入居時の状態に戻す原状回復
原状回復とは、借主が物件を借りた入居時の状態まで戻す工事のことを指します。
これは借地借家法によっても規定されており、テナントが入居中に新たに設置した間仕切りや棚、照明器具などの設備を撤去することが基本的な内容です。
ただし、通常の使用による経年劣化や日常的な損耗については、特別な特約がない限り借主の負担対象とはなりません。
例えば居抜きの店舗やオフィスを借りた場合、借りた当時に存在した内装や設備は残し、それ以降に借主自身が変更・追加した部分だけを撤去することになります。
費用負担を最小限に抑えるためには、入居時の状態を写真や図面などでしっかり記録し、退去時のトラブル防止のため貸主との交渉材料として利用することが効果的です。
契約内容で回復範囲は異なる
退去時に求められる工事の範囲は、賃貸契約書に記載されている内容によって大きく変わります。
契約書に特約として「スケルトンで明け渡す」と明記されていれば、借主はスケルトン戻しを必ず行う必要がありますが、特に明確な記載がなければ原状回復のみが求められます。
そのため、契約内容を事前にしっかりと確認することが重要です。
飲食店など内装工事が多い物件の場合、契約書の記載によっては、配管や電気設備などの細かな部分も借主負担で撤去を求められることがあります。
また、貸主が指定した業者以外に工事を依頼すると、トラブルや追加費用の原因になることがあるため、指定業者の利用義務についても確認が不可欠です。
契約締結時に工事範囲を明確化し、書面で貸主との合意を取っておくことが最善の対策です。
契約書の原状回復条項を確認
契約書に記載されている原状回復条項の内容を細かく確認することが、退去時にトラブルなくスムーズに物件を返還するための最も大切なポイントです。
特に確認すべきなのは、以下の3つです。
- 原状回復義務の具体的範囲
- 通常損耗や経年劣化の負担
- 指定業者の使用義務
これらが明確に記載されていない場合、後から追加工事や費用を請求されるリスクが高まります。
例えば、指定業者の使用義務があるにもかかわらず、他業者で工事を実施した場合、貸主側から工事のやり直しを求められ、二重の費用負担が発生する事例があります。
もちろん、少しでも不明瞭な点や疑問点があれば、決して放置せずに、できるだけ早い段階で貸主や管理会社に問い合わせて明確にすることが不可欠です。
そして、確認した内容や交渉の結果は、必ずメールや覚書といった書面の形で残しておくことを強く推奨します。
通常損耗・経年劣化の具体的な判断基準と貸主負担の範囲
この章では、テナントが物件を退去するときに問題となりやすい「通常損耗・経年劣化」について紹介します。
通常損耗・経年劣化の判断には以下の3つが重要です。
- 通常損耗のガイドライン上の範囲
- 借主負担にならない劣化の具体的事例
- 特約により変わる負担の区分
ガイドラインに見る通常損耗の範囲
テナントが物件を通常通りに使用する中で、時間の経過とともに自然に発生する避けられない傷みや汚れのことを「通常損耗」と呼びます。
これらは、原則として貸主の負担で修繕されるべきものであり、借主が費用を負担する必要はありません。
この判断の拠り所となるのが、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、国交省ガイドライン)です。
具体的には、以下が通常損耗に該当します。
- 普通に生活したり業務を行う中で避けられない壁紙の色あせ
- 床材やカーペットにできる家具跡
- エアコンや給湯器
一方で、飲食店やオフィスでの不注意による大きな傷、ひどい汚れ、破損については通常損耗とは認められず、借主が修繕費用を負担する必要があります。
貸主との間でトラブルにならないように、退去前に国土交通省のガイドラインを事前に確認して、双方が納得できる範囲を明確にしておくことが重要です。
借主負担にならない劣化の具体例
国交省ガイドラインに基づくと、借主が修繕費用を負担する必要がない通常損耗や経年劣化の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 家具の設置によってできた床やカーペットの軽微な凹みや設置跡
- 画鋲やピンなどを使用してポスターを掲示したことによる壁の小さな穴(下地ボードの張替えが不要な程度)
- カーテンレールやブラインドの設置に伴うビス穴(重量物をかけるためのものではなく、一般的なもの)
- 日常生活における日照や照明による壁紙や畳の自然な変色・色あせ
- テレビや冷蔵庫の背面壁に生じる電気ヤケ(黒ずみ)
これらは、物件を通常の方法で使用していれば自然に発生しうるものであり、賃貸借契約において借主の負担とすることは原則としてありません。
同様に、エアコン、給湯器、キッチン設備などが、通常の使用方法にも関わらず経年によって性能が低下したり故障したりした場合も、借主が故意に壊したり、手入れを怠ったことが原因でない限りは、その修繕費用は貸主の負担です。
退去時の貸主との無用なトラブルを避け、スムーズな交渉を行うためにも、入居時に物件の隅々まで写真や動画で記録し、それらを退去時まで大切に保管しておくことが非常に有効な自衛策となります。
特約で変わる通常損耗の負担区分
通常損耗の費用負担に関する取り決めは、契約書の特約条項によって変わる場合があります。
一般的には法律上、自然な劣化に対して借主の負担義務はありませんが、契約時に特約として「通常損耗および経年劣化も借主負担とする」と記載があれば、その特約が優先されます。
特に飲食店やサロンなどの商業テナント契約においては、通常損耗を含め借主負担とする契約が珍しくありません。
そのため、契約締結前に特約の内容を詳細に確認し、リスクが高い場合には負担範囲を明確にしたり、条件を交渉する必要があります。
また退去時に備え、契約内容の理解を深め、原状回復費用の相場を把握した上で、事前に複数の業者から見積もりを取り、比較検討することがトラブル防止につながります。
スケルトン工事が必要か確認する方法
「本当にスケルトン工事まで必要なのか」退去を控えた多くのテナント様が抱える切実な疑問です。
この章では、退去時にスケルトン工事が必要かどうかを確認する方法について紹介します。
スケルトン工事が必要か確認する方法は以下の4つです。
- 賃貸借契約書の原状回復義務の読み方
- 特約事項にスケルトン記載があるか確認する方法
- 不明な点を貸主に確認する方法
- 入居時の写真や図面の重要性
賃貸借契約書の原状回復義務を読む
退去時にスケルトン工事が必要かを判断するには、賃貸借契約書の原状回復義務に関する条文をしっかりと読み込む必要があります。
原状回復とは、一般的には借りたときの状態に戻すことを意味しますが、契約書によっては、スケルトン状態に戻すことが明記されている場合があります。
例えば「借主は退去時、内装設備一式を撤去し、スケルトン状態にして明け渡すこと」と具体的に記載があれば、躯体以外の設備や内装をすべて撤去する必要があります。
逆に、契約書にスケルトン戻しの明確な記載がない場合は、入居時の状態まで戻せばよいことが多く、工事費用を抑えることが可能です。
契約書は貸主との交渉や費用の算出に大きな影響を与えるため、隅々まで目を通しておくことが重要です。
特約事項にスケルトン記載がないか
賃貸借契約書の本文(一般条項)だけでなく、「特約事項」のセクションも必ず確認してください。
スケルトン工事に関する取り決めは、この特約事項に個別の合意として記載されているケースが非常に多いからです。
本文には一般的な原状回復義務しか書かれていなくても、特約で「本契約の特約として、借主は退去時に本物件をスケルトン状態に戻すものとする」などと明確に規定されていれば、それが優先され、スケルトン工事を行う義務が生じます。
特に、飲食店や物販店といった店舗物件の契約では、このような特約が付帯していることが一般的ですので、見落とさないよう細心の注意を払って確認しましょう。
特約にスケルトン記載があった場合、天井や壁、床材だけでなく、配線や配管設備の撤去まで含まれることが一般的です。
スケルトン戻しが義務付けられている場合、撤去工事の範囲や費用相場を複数の業者から見積もりを取って比較し、適切な業者を選ぶことが、工事費用を抑えるための有効な方法です。
不明点は必ず貸主に確認する
契約書や特約事項を読んでいても、工事範囲や撤去の必要な設備について明確でない部分が出てくることがあります。
そのような場合には、決して自己判断をせず、貸主や管理会社に直接確認することが重要です。
例えば「原状回復は借りた状態に戻す」という曖昧な表現があった場合、どの設備を残してよいのか、どの設備まで撤去すべきかが問題になります。
不明確なまま工事を進めてしまうと、後から貸主から追加工事や費用負担を求められるなど、トラブルが発生するリスクがあります。
トラブルを防ぐためにも、貸主への質問はメールなど記録が残る形式で行い、回答を保存しておくことが賢明です。
入居時の写真や図面を保管する
退去時にスケルトン工事が必要かどうかをスムーズに確認・交渉するためには、入居時の物件の状態を写真や図面で記録しておくことが非常に役立ちます。
例えば、居抜きで入居した店舗の場合、入居時に残っていた内装や設備が退去時も残っていて問題ないことを貸主に対し証明が必要です。
しかし、入居時の写真や図面などの記録がないと、貸主との間で認識の違いが生じ、余計な工事費用が発生するケースもあります。
そのため、入居した直後に天井や壁、設備の写真を撮影し、図面や仕様書などと共に保管しておきましょう。
これらの資料は、退去時の費用負担や工事範囲の交渉を有利に進めるための重要な証拠となります。
スケルトン工事の費用相場と内訳
スケルトン工事が必要となった場合、次に気になるのは「一体いくらかかるのか?」という費用面でしょう。
この章では、テナント退去時に行うスケルトン工事の費用相場とその内訳について紹介します。
スケルトン工事の費用に関して、以下の内容を中心に解説していきます。
- 坪単価による費用相場
- 解体撤去・廃棄物処理の費用
- アスベスト除去の影響
- 飲食店など業種による費用の違い
費用相場は坪3万~10万円
スケルトン工事にかかる費用相場は、一般的に坪単価で3万円から10万円程度です。
ただし、これはあくまで目安であり、費用の幅は物件の広さ(坪数)、工事の規模(どこまで解体するか)、内装や設備の複雑さ(造作が多いか、特殊な設備があるかなど)によって大きく変動します。
例えば、比較的内装がシンプルなオフィスや小規模な物販店などでは、坪単価3万円~5万円程度で収まるケースもあります。
一方で、厨房設備や排気ダクト、防水工事など、撤去に手間とコストがかかる設備が多い飲食店や、特殊な内装を施した店舗などの場合は、坪単価が7万円~10万円、あるいはそれを超えることも珍しくありません。
そのため、実際の費用を把握するためには、必ず複数の専門業者に見積もりを依頼し、提示された各社の見積書の内容を詳細に比較検討して、工事範囲や単価が適正であるかを見極めることが不可欠です。
解体・撤去・廃棄物処理の費用
スケルトン工事の主な費用項目として挙げられるのが、解体・撤去工事と廃棄物処理費用です。
まず、店舗やオフィス内の壁、床、天井といった内装材や、造作家具、照明器具、空調設備、給排水設備などを解体し、運び出すための作業費用が発生します。
これに加えて、解体作業によって生じた木材、金属、コンクリートガラ、プラスチックなどの大量の廃材を、法律に則って適正に分別し、中間処理施設や最終処分場へ運搬・処分するための費用が別途必要です。
この産業廃棄物処理費用は、廃材の種類や量、処分場の状況などによって変動し、総工費の中でも少なからぬ割合を占めることがあります。
例えば、廃棄物の量によっては、坪単価で1万円以上の処理費用がかかるケースも珍しくありません。
業者から見積もりを取得する際には、解体工事、搬出作業、廃棄物処理などの各作業項目が詳細に記載され、それぞれの単価や数量が明示されているかを確認し、不明瞭な点や一式計上されている項目については、その内訳を必ず質問するようにしましょう。
これにより、不当な上乗せや過剰請求のリスクを減らせます。
アスベスト除去で費用が増加
特に注意が必要なのが、解体する建物や内装材にアスベスト(石綿)が使用されているケースです。
アスベストは過去に建材として広く利用されていましたが、健康被害のリスクがあるため、現在はその除去作業に法的な規制があり、専門的な知識・技術と許可を持つ業者でなければ行うことができません。
もしアスベストが発見され、その除去作業が必要になった場合、通常の解体費用に加えて、飛散防止対策、作業員の保護具、特別な廃棄物処理などのための費用が別途発生し、工事費用全体が大幅に増加する可能性があります。
追加費用は、アスベストの種類や使用箇所、範囲によって大きく異なり、坪あたり数万円から十数万円単位で上乗せされることもあります。
一般的に、2006年(平成18年)以前に建てられた建物、特に昭和時代の建築物では、壁材、天井材、床材、配管の保温材などにアスベスト含有建材が使われている可能性が否定できません。
そのため、該当する年代の建物でスケルトン工事を行う場合は、必ず工事着手前に専門業者によるアスベストの事前調査を実施し、その有無と必要な対策を正確に把握しておくことが極めて重要です。
これを怠ると、工事途中でアスベストが発覚し、工期の遅延や予期せぬ高額な追加費用が発生するリスクがあるため、計画段階での調査を強く推奨します。
飲食店は費用が高くなる傾向
飲食店の場合、スケルトン工事の費用は他の業種と比較して高額になる傾向があります。
その理由としては、厨房設備やグリストラップ、排気ダクト、給排水管など撤去に手間がかかる設備が多く存在するためです。
また、油や食材による汚れが建物に浸透している場合、通常の内装よりも入念な清掃や特殊な処理が必要になることもあり、これが費用を押し上げます。
飲食店の退去時には、居抜き譲渡による設備の売却を検討すると、工事費用を大幅に削減できる可能性があります。
スケルトン工事費用を安く抑えるコツ
高額になりがちなスケルトン工事は工夫や交渉次第で、費用負担を軽減できる可能性があります。
この章では、退去時に必要となるスケルトン工事の費用を抑えるための効果的な方法について紹介します。
費用を抑えるポイントは以下の3つです。
- 複数の業者から相見積もりを取る
- 厨房機器や店舗設備を買取業者へ売却する
- 指定業者以外の業者を利用できるか確認する
複数業者から相見積もりを取る
スケルトン工事の費用を抑えるためには、複数の業者から相見積もりを取得することが非常に効果的です。
スケルトン工事の費用は、撤去する設備や物件の状態、業者の設定価格などにより大きく異なります。
そのため、同じ内容の工事でも業者によって見積もり金額に大きな差が出る場合があります。
一般的には、少なくとも3社程度から見積もりを取ることで、市場の適正な価格を比較検討することが可能です。
また、各業者に詳細な見積書を提出してもらうことで、不明瞭な工事内容を避けることもできます。
単に価格が安いという点だけでなく、業者の過去の実績、担当者の対応の丁寧さや専門知識、万が一の事故に備えた保険加入状況なども含めて、総合的に信頼できる業者を選ぶことが肝心です。
厨房機器などを買い取り業者へ売却
特に飲食店や厨房設備が充実している店舗の場合、設備や厨房機器を買取業者に売却することでスケルトン工事の費用負担を軽減することが可能です。
厨房機器や業務用冷蔵庫などは、中古でも一定の需要があり、状態が良好であれば高額な買取が期待できます。
通常、これらの設備を廃棄処分する際には、解体費用や産業廃棄物としての処分費用が発生しますが、買取業者に売却できれば、これらの費用が不要になるだけでなく、売却益を得ることも可能です。
その売却益をスケルトン工事の費用に充当すれば、実質的な負担額を大きく減らせます。
ただし、売却時には複数の買取業者に査定を依頼して、適正な価格で買い取ってもらえる業者を選定することが大切です。
査定は無料で行っている業者がほとんどなので、積極的に活用しましょう。
指定業者以外の利用可否を確認
スケルトン工事の費用を抑えるには、契約書に記載されている「指定業者」以外の業者を利用できるかどうかを確認することも重要なポイントです。
貸主が指定する業者は競争がないため、一般的に市場価格よりも高めの価格設定になることが多いです。
しかし、契約書に指定業者の利用が明確に義務付けられていなければ、自身で選んだ業者に依頼することが可能な場合があります。
この場合、複数の業者に相見積もりを依頼することで、工事費用を抑えられます。
契約時や退去を検討する際に、必ず貸主や管理会社に指定業者の利用義務があるかどうかを事前に確認しておくことが必要です。
スケルトン工事で注意すべきポイント
スケルトン工事は、費用だけでなく、その進め方にも注意すべき点がいくつかあります。
この章では、スケルトン工事をスムーズに進めるための注意点を紹介します。
具体的に押さえておくべきポイントは以下の4つです。
- 貸主との工事範囲・負担区分の明確化
- 退去日に間に合わせるためのスケジュール管理
- 貸主の立ち会いによる工事内容の確認
- 事前のアスベスト調査実施
貸主と工事範囲・区分を明確に
スケルトン工事を行う際には、工事範囲や費用負担の区分を貸主と明確に決めることが非常に重要です。
たとえ契約書に「スケルトン戻し」と記載があっても、「どこまでをスケルトンと見なすか」の解釈が貸主と借主で異なる場合があります。
例えば、天井裏の軽鉄下地は残してよいか、床下の配管はどの深さまで撤去するかです。
このような認識のズレを放置したまま工事を進めてしまうと、工事完了後に貸主から「撤去が不十分だ」「ここも解体すべきだった」といった指摘を受け、追加工事やそれに伴う追加費用が発生する典型的なトラブルにつながりかねません。
例えば、借主は壁の撤去までと考えていたが、貸主は壁の向こう側にある古い配管の撤去までを求めていた、といったケースです。
このようなトラブルを避けるためにも、事前に貸主と詳細に打ち合わせを行い、取り決めた工事範囲を必ず書面に残し、双方で署名捺印を行っておくと安心です。
退去日から逆算した工程管理
スケルトン工事は、退去日から逆算して余裕を持った工程管理を行うことが大切です。
特に飲食店や設備が多い店舗などでは、撤去作業に予想以上の時間を要することが多く、工事が予定より遅れるケースも少なくありません。
工事が遅れると、退去期限を超過し賃料の追加負担や違約金が発生するリスクがあります。
これを防ぐためには、工事業者と詳細な打ち合わせを行い、解体や撤去にかかる実際の日数を正確に把握した上で、早めに着手するようスケジュール調整を行う必要があります。
解体工事には貸主も立ち会う
解体工事の最終確認は、必ず貸主にも立ち会ってもらうことが重要です。
貸主が立ち会わずに解体工事を終えた場合、後日になって「撤去すべき設備が残っている」「配線が撤去されていない」といった指摘を受け、再工事や追加費用が発生するケースがあります。
このような事態を確実に回避するためには、工事完了後、速やかに貸主に連絡を取り、双方の日程を調整した上で、必ず現地で一緒に工事箇所を一つひとつ確認しましょう。
そして、貸主から「契約通りの原状回復(またはスケルトン化)が完了した」という確認を得られたら、その旨を記した「完了確認書」や「明渡確認書」といった書面に、日付と共に双方で署名・捺印し、一部を控えとして保管しておくことを強く推奨します。
これが、後のトラブルを予防する最も確実な証拠となります。
アスベスト含有建材の事前調査
特に築年数が古い建物の場合は、解体前にアスベスト含有建材の調査を行うことが不可欠です。
アスベストが発見されると専門業者による特別な処理が必要となり、撤去費用が大幅に増加するとともに、工事期間も延長される可能性があります。
調査をせずに解体を進め、途中でアスベストが発見されると工事がストップし、大きな損失につながることもあります。
安全面とコスト管理の両方を考慮して、工事前に必ず専門業者へアスベストの調査を依頼し、結果を踏まえて計画を立てることが重要です。
スケルトン戻しを回避する居抜きとは
高額な費用と手間がかかるスケルトン戻しを回避し、かつ双方にメリットをもたらす可能性のある方法が居抜きです。
この章では、居抜きという方法を活用して、スケルトン戻しを回避する方法について紹介します。
居抜きを利用すれば、次のようなメリットが得られます。
- 内装や設備をそのまま残して退去できる
- 解体費用を削減し、売却益を得られる可能性がある
- 貸主との交渉や後継テナント探しが必要になる
内装や設備を残したまま退去
居抜きとは、テナントが店舗やオフィスの内装や設備を撤去せず、そのままの状態で退去し、後継テナントに引き継ぐことを言います。
スケルトン戻しでは内装や設備の解体工事費用が必要ですが、居抜きを活用することで、これらの費用を大幅に抑えることが可能です。
特に飲食店の場合は、厨房設備や空調設備などの費用負担が大きいため、居抜きにより設備の撤去費用を節約できることは大きなメリットになります。
ただし、この魅力的な居抜き退去を実現するためには、物件の貸主の承諾が必要です。
そして内装や設備を引き継いでくれる次の借主を見つけることが不可欠であり、そのためには計画的な準備と関係者との丁寧な調整・交渉が求められます。
解体費用削減と造作売却益
居抜き退去が実現した場合の大きなメリットは、解体工事費用が不要になることだけではありません。
さらに、残していく店舗の内装や設備(造作)を、次のテナントに対して有償で譲渡(売却)することで、思わぬ収益を得られる可能性があります。
これを「造作譲渡」と言い、その売却代金は「造作譲渡料」や「店舗譲渡料」などと呼ばれます。
例えば、比較的新しくて状態の良い飲食店の厨房機器一式、デザイン性の高いテーブルや椅子、高性能な業務用エアコン、こだわりの照明設備などは、次のテナントにとって初期投資を抑えられる魅力的な要素となるため、中古市場の相場に応じた適正な価格で買い取ってもらえることがあります。
この造作譲渡によって得られた収益は、スケルトン工事をしていればかかったであろう費用との差額だけでなく、次の事業展開のための移転費用や運転資金に充当することも可能です。
居抜きでの退去を具体的に考え始めたら、まずはこれらの造作物の価値を把握するために、店舗専門の買取業者や居抜き物件を扱う不動産業者に査定を依頼し、どの程度の売却益が見込めるのか、早めに試算しておくことが賢明です。
これにより、貸主や後継テナント候補との交渉も有利に進めやすくなります。
貸主の承諾と後継テナント探し
居抜き退去をスムーズに、そして確実に成功させるためには、以下の2つが重要です。
- 貸主の承諾
- 後継テナントの確保
まず、現在の内装や設備を残したまま退去することについて、物件の所有者である貸主から書面による明確な承諾を得なければなりません。
貸主によっては、物件の管理方針や次のテナントの業種選定の意向などから、居抜きを認めないケースもありますし、契約書に「居抜き禁止」の特約が盛り込まれている場合もあります。
そのため、退去の意思を固めたら、できるだけ早い段階で貸主に相談し、居抜きでの退去が可能かどうか、可能であればどのような条件があるのかを打診・確認することが不可欠です。
そして、貸主の承諾が得られたとしても、実際に内装や設備を引き継いでくれる後継テナントが見つからなければ、契約通りに原状回復やスケルトン戻しを行わざるを得なくなり、期待していた費用削減は実現できません。
したがって、貸主との交渉と並行して、自ら後継テナントを探す努力をするか、居抜き物件に強い不動産仲介業者に依頼して、積極的に後継テナントの募集活動を行う必要があります。
これらを計画的に進めれば、トラブルを未然に防ぎ、円満かつ経済的な退去を実現できるでしょう。
居抜き専門業者に相談する
居抜きでの退去を検討する際には、居抜き専門業者への相談が効果的です。
専門業者は後継テナント探しや設備の売却、貸主との交渉まで幅広くサポートしてくれます。
特に飲食店や美容室など、設備が多く工事費用が高額になりがちな店舗では、専門業者に依頼することで、短期間で次のテナントが決まり、費用面や時間面の負担を軽減できるケースも多くあります。
退去が決定したら早めに業者に相談し、適切な計画を立てることで、居抜きによるメリットを最大限に活かすことが可能になります。
まとめ
原状回復とスケルトン戻しは混同されやすいですが、工事範囲や費用が異なります。
契約書の条項を正しく確認し、スケルトン工事が必要かどうか、どの範囲の内装や設備を復旧する必要があるのかを事前に貸主へ確認しましょう。
費用削減には相見積もりや居抜き譲渡が効果的です。
工事範囲の明確化や入居時の記録保存など、早めの準備と交渉でトラブルなくスムーズな退去が実現します。
«前へ「退去費用はいくら?原状回復ガイドライン&負担割合表で解決!」 | 「敷金トラブル回避!退去時の原状回復・ハウスクリーニング相場と対策」次へ»